「0021」 論文 数の本質から見たお金という人類最強の価値尺度−ratio論を手がかりとして(2) 高野淳筆 2009年4月7日
3.数の意味づけ
以上見てきた通り、ratioの根幹には「数」がある。以下では数というものに「意味づけ」をしてみようと思う。数学史家は別として、数学者は数の意味などというものを教えてくれない。数学は意味を捨てて、いわば血を抜き、肉を削ぎ落とし骨格だけを残したような学問である。意味などと言うものは邪魔者と考える。専門家は一般人の素朴な理解を助ける仕事をもう少ししてもいいと思うのだが。
数の「意味づけ」とは、あくまでも私の「意味づけ」である。数の概念の発生といったことに対しては史実かどうかの検証ができないからだ。それに「意味づけ」とは各人がそれぞれおこなうものだ。とはいえ全く勝手な議論ではない。数学史上の事実は「意味づけ」とは別にきっちり押さえておく必要がある。その上でなおこのような「意味づけ」をすることは意味があると考える。受験生など数学を学ぶ側からすれば、「意味」を思い描いて学習できたほうが、単なる記号操作を続ける苦痛感を多少取り除ける。あるいは、その後の実生活では一度も使わない事柄を学ばせられるという空虚感を減少できる。
主な主張を2つにまとめてみた。
(1)数というものは人間が生き残るため必要に迫られ使い出した道具だ ったはずだ
(2)数を数えるという方法は、その後拡張されて、「量」や「向き」も 取り込んで扱える道具となった。
以下で細かく見ていくことにする。
(1)数というものは人間が生き残るため必要に迫られ使い出した道具だったはずだ
人類が最も切実に数える必要性に迫られた場面とは、食料貯蔵とその管理だったのではないか。冗談っぽく言えば、冬を越せずに備蓄食料がゼロになってしまえば死に絶えてしまうので、ゼロの発見はなかなか広まらなかったのだ。
食料に余剰が生じれば個人・家族・共同体などの所有物が生まれる。所有物(財産としての家畜や農産物など)が失われていないかどうか確認する必要性から数えるという行為が生まれてきた可能性もある。「1、2、3、たくさん」などのようにわずかの数詞しかない集団の例が報告されている(注1)。これは食糧が豊富で、貯蔵や所有の必要がないような地方・社会では、数える必要性がないからではないか。数の概念は、文化段階が進むとともに発達したというよりは、切実な必要性に迫られて発達したはずだ。
交易が行われるようになると取引で数量をごまかされないために、取引者相方で納得いくよう取引物同士をつきあわせるという方法が生まれてきたのではないか。これが1対1対応だ。対応の一方の側に抽象物(名詞)を持ってきたものが自然数といってよい。1対1対応の確実さは信頼性を生み、信頼性を失わないまま抽象化できたことで、数は信頼性と利便性を持つ道具となった。遠山啓著『数学入門(上)』(岩波新書、1959年)から引用する。
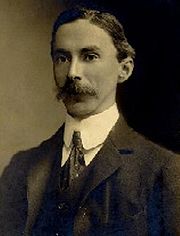
バートランド・ラッセル(Bertrand Russell)
(引用はじめ)
イギリスの数理哲学者バートランド・ラッセルは「2日の2と2匹のキジの2とが同じ2であることに気づくまでには限りない年月が必要だった」といっている。たしかにラッセルのいうように2という数は、2個の卵、2匹の犬、2人の人間、2羽の鳥、2冊の本に共通のものである。だから2個の卵の一つ一つを2本の木でおきかえても、2であることに何の変わりもないのである。このように卵の一つ一つを1本ずつの木と結び付けることを一対一対応というが、2はこの一対一対応という手続きをほどこしても変わらないのである。
一対一対応によって変わらないという事実を利用すると、数えにくいものを数えやすいものでおきかえるという方法が生まれてくる。(4−5ページ)
(引用終わり)
(2)数を数えるという方法は、その後拡張されて、「量」や「向き」も取り込んで扱える道具となった。
複素数までの数の中には「数」「量」「向き」の3つの違った要素が取り込まれている。
以下、自然数、分数、無理数、マイナスの数、虚数をとりあげて意味づけしてみる。ここでは数の拡張というものが、四則演算を行えるようにするためあるいは方程式を解く必要性からなされていった歴史的経緯とは別に、それぞれの数をどのような観点からみるとスッキリ理解できるかという視点でまとめた。歴史的経緯についての、また数の歴史についての諸書(たとえば注1に揚げた文献など)に譲る。
1)数える
<<自然数>> <<0>>
数(自然数)を数えるとは、一定間隔で、一定方向に数えるという前提に立っている。これは数が複素数まで拡張された後でふりかってみてわかったことだ。このあたりまえ過ぎて意識しないような前提がこの後の議論の中心となる。ところでゼロが数としてなかなか認識されなかったのは、ないものは数える対象にならなかったからだ。数の最初を1とすると0は何か。量の考え方に立てば0は1とともに「単位の頭と尻尾」を決めるものだ。向きの考えに立てば座標の中心ということになる。ただ集合論は、無いもの(空集合)を数えて自然数をつくりだすという離れ業をやっている(注2)。
英語の勉強を始めると、名詞の中に数えられる名詞(可算名詞countable)と数えられない名詞(不可算uncountable)が出てくる。数えるとは、輪郭がはっきりしているものを対象とした行為ということになる(注3)。可算/不可算の話を持ち出したのは、この後に行う「量」の議論とつなげるためである。ちなみに、数えられる/数えられないという概念は、量子力学の量子という概念にも反映されている。量子論の発端は、エネルギーのように連続的に変化する量と考えられていたものにも、実は最小単位(量子)があり一つ二つと数えられるというところにあった。そう考えた方が観測結果をうまく説明できるということだった。もう少し大きなレベルで言うと、コップの水は輪郭がなく1つ2つと数えられないが、分子レベルで見れば原理上は水分子1個、2個と数えられるというのと同じだ。エネルギーについてもこのように言えたというのは驚きではないか。できれば何でも数えたいわけだ。
<<分数>> <<有理数>>
自然数を数える前提の一つ「一定間隔で」という条件を崩すと、今までの数と数の間にも「新しい数」=「分数」が出てくる(ここで、無理数も同時に出てくるが、無理数についてはこの後、量として捉える項目で述べる)分数は、自然数を割って出来た今までにない数のようでもあるが、比の概念を使えば、自然数から作り出せる。たとえば、「我が軍200騎に対して、敵は100騎。敵は我が軍の半分ですぞー」などというように。だから、分数は「数(数える)」の範疇に入れていい数である。
2)量(輪郭のはっきりしないものまで数えてしまいたいという試み)
<<無理数>> <<実数>>
私たちが無理数に最初に出会うのは、ピタゴラス(Pythagoras of Samons)の定理に関連して√2について学ぶ時だろう。ピタゴラスの定理は長さや面積など関係する話なので、無理数というものが長さや面積といった「量(輪郭のはっきりしない、数えられないものに)」と密接にかかわる数だと推測できる。

ピタゴラス
もう一つの無理数の代表格πも、円周と直径の「長さ(数えられないもの)」の比という定義だ。無理数(有理数と無理数を合わせて実数)は、液体など、輪郭のないもの(不可算名詞:とびとびでなく、切れ目無く値が変化しうる量)を何とか数字で表そうと試みたときに出てきてしまった数だ。不可算量を数えようとすれば、基準量を決めて、その何倍になっているか(比をとる)という形で表すのがいいだろう。
そして、無理数とは、この基準量との比をとったとき、分数では書き表せない数だった。小数で示そうとしても、数字をいくつ連ねようと永久に書き終わらない数だった。つまり番号では指定できない数、数なのに数字で書き尽くせない定義矛盾のような数である。それでもたとえば√2は一辺が1の正方形の対角線の長さというように、目に見える形で示すことができるので、それは数として認められた。「量」に番号を振ろうという試みは理論の上では破綻した。しかし現実問題としては、長さや量を量る場合は、必要な精度まで計測して、あとは打ち切ってしまうので、無理数が量の把握を決定的に妨害するようなことはなかった。
無理数はirrational numberの訳で、「整数比で表せない数」という定義そのままの名前がついている。ここでもratioは「比」であって「理」とは訳さない方がよかった。だからといって「無比数」と直しても具合がわるい。既に見たように、√2は正方形の一辺の長さと対角線の比だし、πは円周と直径の比だから、比がないという言い方では説明不足となる。
有理数と無理数をあわせた実数により、連続的に変わる「量」もすべて数の中に取り込まれた(無理数はいつまでたっても数字で書き尽くせない数であるという矛盾は、自然数の無限を超える無限があるという形で回避される)。
3)向きという解釈(後ろ向きにも横向きにも数があった)
<<マイナスの数>>
「一定方向に」数えるという前提を崩したときにまず出てくるのが、マイナスの数である。マイナスの数とは、今までの数える向きとは逆向きに数えた場合につくり出される数だ。マイナスの数の起源は「借金」だろう。借金を踏み倒してしまえば、自分にとってマイナスだったものがプラスに変わる。だから借金ができる世界では、数の大きさだけでなく、数える方向も重要なのだ。
マイナスの数は、温度計のように基準点としてのゼロを持ち込むことで、目に見えるようにすることができた。「量」と組み合わせれば、マイナスの量も考えられる。はじめに決めた自然数の向き(この向きをプラスの向きとする)に対して、マイナスの向きを正反対と決めるので両者は直線上にならぶ(数直線)。マイナスの数は足し算を通じて、それまでの数(プラスの数)と行き来できる。
<<虚数>>
虚数に感じる胡散臭さはどこからくるのだろうか。もともと無いといっていたものを、都合で勝手に作ってしまうことからくる不信感か? それなら無理数やマイナスの数もないと言われていた数ではなかったか。虚数に感じる嘘くささは、大半の人にとって仕事でも日常でも虚数を見たり使ったり意識する機会がないからだろう。それは、「1、2、3、たくさん」と数える人にとって100という数字にリアリティーがないのと同じだと思う。
もともと数は思考の道具であるから、在るとか無いとかという実在の議論とは無縁であると悟ればいいのだ。「神が整数を作った。あとは人間の産物だ」とはレオポルト・クロネッカー(Leopold Kronecker、1823-91)の言葉として有名である。私はこれを「整数だけがこの世にある」という意味だと誤解していたが、そのようには言っていない。

レオポルト・クロネッカー
マイナスの数を後ろ向きに数えた数とすれば、虚数とは真横(プラスの向とは、90度の方向)に数えたときに並ぶ数だった(注4)。
虚数は掛け算を通じて実数との間を行き来できる。足し算だけでは実数と混じらない。つまり複素数(実数と虚数を組み合わせた数)はa+bi(a,bは実数、iは虚数単位)という形で書かれるが、aとbは+で結ばれているにもかかわらずaとbを足し合わすことはできない。複素数とは実数と虚数という相容れない2つの数が掛け算を通じて絡み合いながら共存している数だ。そして複素数では2つの数の間で大小は決められないのである(注5)。
4.まとめ(rationalismの行き過ぎへの歯止め・数字の悪用への用心)
ratioは合理、reasonは理性と訳されたてきた。では何がrationalで、reasonableなのかと問われると誰にもはっきりと答えられなかった。2002年に副島が示したとおり、哲学者の認識論的な「理性」の議論をやめて、ratioを、選択論的な判断基準ととらえればその意味は極めて明確なものとなった。投入する労力(エネルギー、お金)と得られる成果(エネルー、お金)を比較して割に合う場合は実行するという判断・態度こそrationalismだった。
個数の比較のように数の大小で判定するやり方は誰の目にも明らかな結論が得られるので信頼感を勝ち得た。数は量も扱えた。その確実性や利便性から強力な道具としての地位を確立した。この数の力を現実世界で用いるため、人類はお金というシステムを作り出してさまざまな価値を数字で表わそうとしてきた。
お金というシステムの中でrationalな方向を突き詰めていくと、拝金・強欲に行き着いてしまう。人類の手にした強力な道具である「数」を手放すわけにはいかないが、今や数の扱いには節度が求められるところまできた。数というものを本源までさかのぼってチェックしてみると、複素数という日常とは縁遠い数の中にも教訓を読み取ることができる。本来違う性質を持つ数字は足し合わせて評価できないものであって、
あらゆる価値をお金で評価することはできないという当たり前の結論が得られる。複雑化専門化した今日では、数字の悪用も容易である。数に「万人の納得」という本来の役割を持たせるためはわれわれが数字を批判的に見ていく習慣を養っておかなければならない。
(脚注)
(注1)「1、2、たくさん」について
・ドゥニ・ゲージ著、南条 郁子訳、 藤原 正彦監修『数の歴史』(創元社、1998年)
(引用はじめ)
「一部の民族にとっては、「1」と「2」と「たくさん」という3種の「数」さえあれば、たいていの用は足りた。」
(引用終わり)
・遠山啓『数学入門(上)』(岩波新書、1959年)
(引用はじめ)
「極端な例は南米ボリビアのチキト族であって、1に当たる「エタマ」という数詞しか持っていないという。・・・また「2」を「ポエタラロリンコアロアク」という長たらしい数詞でよんでいるアマゾン流域のヤンコ族も、2という数をあまり使う機会がないので、こんな長たらしい数詞が生き残っているのだろう。2をひんぱんに使う必要があったら、もっと省略された数詞が生まれてくるはずである」(8ページ)
(引用終わり)
・ジョン・タバク著、松浦俊輔訳『はじめからの数学3 数、コンピューター、哲学者、意味の探究』(青土社、2005年)
(引用はじめ)
「オーストラリアの原住民の中には、歴史上も最近になるまで、ほとんど数なしで生きてきたと言われる部族もある。昔の人類学者が、オーストラリアの原住民には6あるいは7を超える数は区別しない部族があること、数え方は「1,2,3,4,5,6,たくさん」と進むと言っている。こうした昔の報告を解釈するときは気をつけなければならない。文化や言語の違いのせいで、人類学者が調べている民族と効果的に意志を伝えあうのは難しかったし、その観察結果も、オーストラリアの原住民が別の文化で過ごしていて、今やそれに応じて適応してしまっていると、確認できない。ともあれ、すべての文化が体系的な数え方を発達させたわけではないということは、まず疑いはない。」(22ページ)
(引用終わり)
・ジョルジュ・イフラー著、弥永 みち代、後平 隆、 丸山 正義訳『数字の歴史』(平凡社、1988年)
(引用はじめ)
「アフリカやオセアニア、アメリカ大陸の一部の原住民は、少なくとも今世紀初頭まではかなり初歩的な段階にとどまっていたが、彼らは<1>、<2>、<3>、<4>という数しかはっきりと知覚しておらす−彼らの言葉のうちではっきり表現されていいない−その他の数は彼らにとっては漠然とした総体的観念であり、もっぱら物の多数性に結び付くものだったのである。
たとえばゾンマーフェルトによると、オーストラリアのアランダ族は、いわゆる<数名称>として二つの語しか知らなかった。<1>を表すnintaと対を表すtaraとである。<3>と<4>については、tara-mi-nita(<2>と<1>)と、tara-ma-tara(<2>と<2>)と言っていた。しかしアランダ族の数列はそこで止まってしまう。というのもtara-ma-taraから上については、<たくさん>を意味する言葉を用いていたからである。」(12ページ)
(引用終わり)
(注2)竹内外史『新装版 集合とはなにか』(講談社、2001年)、79ページ
(注3)大西泰斗・ポール・マクベイ『ネイティブスピーカーの英文法』(研究社、1995年)
(引用はじめ)
非可算名詞の特徴として、「形がない」「境界線がはっきりしない=まとまりがない」がすぐに思い浮かぶでしょう。(31ページ)
(引用終わり)
(注4)虚数は実数に対して90°の向きに並んでいることについては、たとえば
瀬山士郎『読む数学』(ベレ出版、2006年)、25ページを参照。
(注5)ドゥニ・ゲージ『数の歴史』pp.101-102
(引用はじめ)
「数の範囲が複素数まで広がったため、2つの数を比較することができなくなった。実数ならどんな数をとっても、つねに大小が比較できる。どちらか一方が他方より大きいか、さもなければ等しいからだ。だが複素数ではこうはいかない。2つの複素数zとz’ではzがz’より大きくも小さくもなく、その上等しくもないということが起こりうる。要するに比べること自体が無意味なのだ。」(101−102ページ)
(引用終わり)
(終わり)