「0101」 論文 サイエンス=学問体系の全体像(21) 鴨川光筆 2010年9月13日
文化人類学の父はエドワード・タイラー
文化人類学が独自に作り上げた進化理論のことを、「社会進化論(Social Evolution Theory)」という。進化理論を人間に当てはめた考え方である。
この社会進化論を初めて提唱したのは、「文化人類学の父」と呼ばれるエドワード・タイラー(Edward Tylor)である。今私たちが普段思い描いている、人間の社会的進化に関する「常識」を作ったのはこのタイラーである。

エドワード・タイラー
エドワード・タイラーは、一八七一年、『原始文化』 (Primitive Culture)を著す。この作品でタイラーは、人間の原始的世界観の起源と、進化の跡の復元を試みた。(『文化人類学事典』 ぎょうせい 四三〇ページ)
同書でタイラーは、画期的な思想を生み出す。タイラーは、人間の発展段階は野蛮(savage)・未開(barbarian)・文明(civilized)という三段階があり、文明状態がその頂点に位置するのだと主張した。
テイラーは『原始文化』の中で未開人と野蛮人の定義を初めて行った。未開人とはバーバリアン(barbarian)の翻訳で、野蛮人とはサヴェージズ(savages)の翻訳である。この二つを混同して解釈してはならない。タイラーは文明を頂点とする文化の階級制度を作り上げた。「文明人は野蛮人よりも賢明で有能であるばかりでなく〜未開人はその中間に位置する」。(『文化人類学20の理論』 綾部恒雄編 弘文堂 四ページ)
タイラーの言いたいことは、ヨーロッパ人は文明人であり、野蛮人(サヴェージズ)がもっとも下等な段階で、それが進化した状態が未開人(バーバリアン)だということである。文明人が頂点で、以下、未開人、野蛮人と続く。
この文明人を最終ゴールにする発展段階は、単系・直線的進歩といい、もともとはジャン・バプティスト・ラマルク(Jean-Baptiste Lamarck)の提唱した進化論であった。「シングル・アンド・ユニリニアル・プログレス(single and unileal progress)」という。ラマルクは生物学のところで説明した。生物学という言葉を作ったのがラマルクである。

ラマルク
リニアー(linear)という言葉をなおざりにしてはいけない。渡部昇一氏や池上嘉彦(いけがみよしひこ)氏、外山滋比古(とやましげひこ)氏をはじめとした英語系の言語系学者は、「英語という言葉は直線的な、リニアーな言語である」ということをたびたび言うが、リニアーとはそのような単純な解釈ではとらえられない。
リニアーとは、リニア・モーターカーの「リニア」である。原因・結果のまっすぐな連なりである。原因・結果とは「逆からの流れは絶対にありえない」というきわめて人為的な考え方である。
原因があって初めて結果があるのであり、結果が先にあって原因があるというのは成立しない。この思想に関しては中世を通じて、とくにイスラムの知識人の間で激しい思想対立となって今日に至っている。キリスト教、ユダヤ教でも同様である。
「原因・結果」のことを「コーザリティ(cusality)」あるいは「コーゼイション(causation)」と言う。これが認められたことで学問が進歩していった。タイラーも近代学問の潮の流れに沿って、当然のごとくそれを導入したのである。
ところが英語の論理にしても、リニアーという考え方にしてもそれだけの単純なものではない。原因結果、リニアーとは大きくは「コロラリー(corollary)」(系、体系)「システム(system)」に組み込まれた考え方なのである。
系、システムとは、力のバランスの取れた状態のことで、これを「エクィリブリアム(equilibrium)」という。このことを私は再三主張してきた。全ての学問・思想は「エクィリブリアム」によって本質が明らかになる。英語の発想にも当然「エクィリブリアム」が入っている。
英語で理由を表す前置詞であるフォー(for)は「価値の等価交換」を表す。ビコーズ(because)もそうである。原因・理由を述べると言うことは、「その結果に至った等価な価値を提示するということ」なのである。だからバランスがとれていなければならないのだ。
タイラーの述べた「ユニリニアー( unilinear )」というのは、エクィリブリアムのように原因・結果のつながりが複数あるのではなく、一本の線としてつながっていく、という考え方である。実にシンプルな、その他の可能性を全て捨てたモデルである。
ラマルクの提唱した進化理論を社会進化論として人類学に導入し、最も単純な原因・結果の論理で、文化・社会の進化を理論付けた試みは、出来る限り無駄な要素を捨象して(neglect ネグレクト)、文化人類学を学問的に基礎付けた点で評価されたのである。
社会進化論のルイス・モルガン
タイラーのほぼ同時期にもう一人、文化人類学を基礎付けた人物が登場した。ルイス・モルガン(Lewis Morgan、一八一八〜一八八一年)である。モルガンもまた社会進化論を導入し、先の三つの原則を下敷きにして、より細かい分類を文化進化の段階に施した。
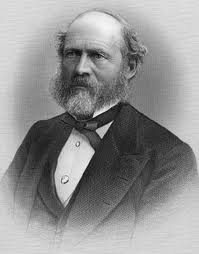
ルイス・モルガン
モルガンは一八七七年、タイラーの『原始文化』と並ぶ、文化人類学の開始を告げる書『古代社会』(The Ancient Society)を発表する。
モルガンの分類は、モンテスキューの、野蛮、未開、文明の三段階を踏襲し(実はこのアイディアはタイラーのオリジナルではない。一八世紀の啓蒙思想から発生している)、野蛮と未開の段階をさらにそれぞれ「上期、中期、下期」の三つの段階に分けた。

モンテスキュー
野蛮段階の下期は、人類の始まりである。中期は魚食と火の使用。上期が弓矢の発明である。未開段階の下期は、土器の発明。中期は、東半球では家畜の飼育、西半球ではトウモロコシと植物の栽培が始まるとした。
未開段階の上期で、ついに鉄器の使用が始まり、文字の発明のよって文明に至る。(『文化人類学事典』 四三一ページ)
モルガンのこの社会進化論のことを、歴史の単一的解釈、リニアー・インタープリテーション(linear interpretation)という。
モルガンが後世非難され、彼の理論が学問的信憑性に欠けるとされたのは、人間の婚姻体系も、この段階による「進化」に当てはめられるとしたことである。
人間の婚姻も、野蛮の段階では、同一世代の乱婚や、兄弟姉妹の集団婚が存在し、そうした混乱した状態から脱却した後、人類は一夫多妻制(Polygyny)を採るようになった。最後に一夫一婦制(polygamy)が婚姻関係を結ぶと言う夫婦制で、文明に達するという理論である。
しかし、モルガン死後、世界中から集積された膨大な人類学的資料によって明らかになったことは、乱婚も集団婚も認められる社会は一つもなく、一夫多妻制をとる文明社会が依然存在するという事実であった。イスラム社会がまさにそうである。モルガンの『古代社会』は、現在はあまり支持されていない。
『古代社会』のある部分は、二〇世紀の世界に多大な影響を与えることになる。「生産技術の発達につれて、人類社会が進歩する」という、同書におけるモルガンの考えは、マルクスとエンゲルスが採用し、エンゲルスの『家族・財産および国家の起源』(The Origin of the Family, Private Property, and the State: in the light of the researches of Lewis H. Morgan、一八八四年)は『古代社会』の影響で書かれたものだ。

エンゲルス
マルクスの『経済学批判』(A Contribution to the Critique of Political Economy、一八五九年)も、『古代社会』の影響で書かれたものである、とブリタニカは指摘している。

マルクス
モルガンはフィールド・ワークと親族研究の祖である
モルガンの『血縁および姻族関係』(Systems of Consanguinity and Affinity、一八七一年)は、親族研究の先駆として、後世大きく評価されている。
この研究は、モルガンが北米東海岸のイロクォイ族(The Iroquois)の研究を行い「北米インディアン社会には、ヨーロッパと異なる親族分類様式を発見」したことに端を発する。(『文化人類学事典』 四三〇ページ)

イロコイ族の風習
モルガンはイロクォイ・インディアンの窮状改善に乗り出し、「コルディウスの結び目」という秘密結社を組織する。イロクォイ族の利害の代表者としても活躍し、イロクォイ連合の一部族、セネカの養子となり、「タヤダウークー」という民族名を与えられるまでに現地人に溶け込もうとした。(『文化人類学20の論理』 弘文堂)
社会学、文化人類学はフィールド・ワークを得意とするが、これを初めて行なった人物がモルガンである。チンパンジーの生態を調べるためには、チンパンジーの生きる森に何十年も一緒に生活しなければならない。現在一般的になっている社会学問の徹底した姿勢は、このモルガンから始まった。
モンテスキューの『法の精神』とハーバード・スペンサーの「社会進化論」
タイラー、モルガンの人類社会の発達段階を最初に図式的に示したのは、シャルル・モンテスキュー(Charles-Louis de Montesquieu)である。
モンテスキューは『法の精神』(The Spirit of the Laws、一七四八年)の中ですでに、人類の発達段階を三つに分類している。最も古い狩猟社会は、野蛮な段階(サヴァージ・フェイズ savage phase) であり 、中間の段階である遊牧社会は、未開な段階(バーバリアン・フェイズ barbarian phase)で、頂点が文明社会(シビライズド・ソサエティ civilized society)であるという、三段階の人類社会の進化の類型を提示した。
実はこの社会進化論という考え方は、チャールズ・ダーウィン(Charles Darwin)の『種の起源』(On the Origin of Species)に先立つこと二年前の一八五七年、ハーバート・スペンサー(Herbert Spencer)が著書『進歩について・その法則と原因』の中で唱えたものである。

スペンサー
進化論の中でよく言われる「優勝劣敗(ゆうしょうれっぱい)」「適者生存(てきしゃせいぞん)」「弱肉強食」は、「サヴァイヴァル・オブ・ザ・フィッテスト(survivial of the fittest)」という英語が元であり、スペンサーの造語なのである。日本では、この言葉に上記三つのばらばらの翻訳が当てはめられて、今日に至っている。
スペンサーは、「サヴァイヴァル・オブ・ザ・フィッテスト(環境に最も適応したものが生き残る)」という造語によって、ラマルクらによって唱えられていた「単純なものが複雑なものに進化していく」という進化理論を社会に当てはめたのである。
ダーウィンはそもそもこの言葉を使うのを嫌い、「自然選択、自然淘汰、ナチュラル・セレクション(natural selection)」という言葉を使っていたのである。弱肉強食も適者生存も、ダーウィンとは関係が無い。
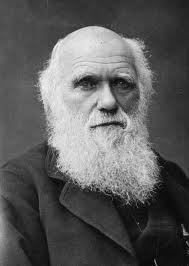
ダーウィン
二〇世紀以降の思想に決定的に影響を与えたダーウィンの思想は、さまざまに批判され、現在では間違ったとらえ方をされることが多い。私たちは、生まれる前から形成されてきた、自分たちの思考の基盤となっているダーウィンとダーウィニズムに関して、もう一度正確な理解をしていかなくてはならない。
ハーバード・スペンサーの言葉は、本来の進化理論とは逸脱した考え方である。しかし、一九世紀の西洋列強による帝国主義政策に「適者生存理論」はよく適合したため、この言葉が広まるようになった。
文化伝播主義―「ザ・グランド・ディフュージョニズム」
社会進化論を導入したタイラーではあったが、彼自身、世界からものすごい勢いで集積されつつあった文化人類学、博物学的情報の集積に触れるにつれ、「文化の伝播(でんぱ)」「ディフュージョン・オブ・カルチュラル・キャラクタリスティクス(diffusion of cultural characteristics)」という概念の導入が必要であることを感じ始めていた。
この考えを「文化伝播主義」(ぶんかでんぱしゅぎ)という。あるいは「超文化伝播主義」(ザ・グランド・ディフージョニズム the grand diffusionism)という。
文化の伝播というと、進化理論とは真逆で、「文化というものは相対的で、お互いが関連して、広がっていったものだ」というような印象を受けるが、実は社会進化論の双子の兄弟である。社会進化論を別の角度から見たものだと考えてもいい。
文化伝播主義とは以下の考え方である。具体的な歴史というものは、必ずしも継続しているとは限らず、文化同士が干渉することもある。文化は集中することもあれば、別々に発達していくこともある。他の民族からの文化を借りて、進化論的な「段階、ステージ(stage)」を飛び越えることもある。
これは、ハーバート・スペンサーの提示した社会進化論の二つ目の原理、「人間の心理の斎一性(uniformity さいいつせい:これはすぐ下で説明する)という考えの限界としてとらえられ、文化伝播主義というもう一つの文化人類学の概念の出発点となった。
「斉一性」(さいいつせい)という言葉が出てくるが、この言葉もきちんと解説している本が無い。斉一性などといわれても、という感じであろう。私もそうであったが、読者の皆さんも、「斉一性」と書かれても、分かったような感じで、読み飛ばしてしまうであろう。
ブリタニカには単純にこう書かれてあった。「ヒューマン・ネイチャー・イズ・ユニヴァーサル(Human nature is universal.)」。これではっきりと分かるであろう。「人間の本性は、普遍的である」というのが正しい。
「人間はどのような地域にいても、環境の影響とは別に、人間に備わった変わることの無い本性が備わっている。この本性は後天的な作用によって変化することは無い。だから人間はどのような環境で文化と社会を生み出しても、必ず西洋人の到達した文明段階に、単一の直線的に(ここでユニリニアーという考えが登場する)到達するように運命付けられている」というのが斉一性であり、社会進化論の正しい理解である。
斉一性とユニリニアーとは切っても切り離せない関係にある。この二つが無ければ社会進化論は成立しないのである。つまり、文化伝播主義も、根っこの部分で進化理論につながっているのである。社会進化理論と文化伝播主義は、「二つの頭を持った竜」のようなもので、尻尾は一つである。
一九世紀末になると、世界各地に散らばったミショナリー、商人、旅行者、探検家、学者たちの多様で膨大な博物学的知識が集積されていった。
その中でも著名なのがサー・ジェームス・フレイザー(Sir James George Frazer)の『金枝篇』(きんしへん、ゴールデン・バウ Golden Bough)である。

フレイザー
こうした事実の集積は社会進化論者にも取り上げられ、彼らの理論の部分的補足として採用されていった。
ところが世界各地の文化に関する情報の洪水に触れるにつれ、文化のリニアー的発達を切断する現象が頻繁に見られたのである。そこに登場したのが文化歴史学派というドイツ人の小集団である。
ドイツ文化歴史学派―オーストロ・ジャーマン・ディフージョニスト
文化伝播主義は、フリッツ・グレーブナー(Fritz Graebner)とヴィルヘム・シュミット(Wilhelm Schmidt)ら「文化歴史学派」(カルチャー・ヒストリカル・スクール Culture Historical School)から始まる。

シュミット
ブリタニカにはこの二人の名前から始まっているが、その前に、一九世紀のフリードリッヒ・ラッツェル(Friedrich Ratzel、一八四四〜一九〇四年)という人文地理学者の功績が大きい。(『文化人類学事典』ぎょうせい 四三四ページ)

ラッツェル
彼らは、後に述べるボアズらのアメリカ歴史学派の大きな集団に対して、非常に小さい「オーストリア・ドイツ文化伝播主義者」(オーストロ・ジャーマン・ディフュージョニスト Austro-German Diffusionist)と呼ばれた。
彼らは文化伝播主義を成立させる、四つのキーワードを生み出すことになる。「形態基準(けいたいきじゅん)」「量的基準(りょうてききじゅん)」「文化圏」「文化層」この四つが、文化伝播主義から生まれた言葉である。
「形態基準」はフリードリッヒ・ラッツェルの生み出した言葉である。ラッツェルは、アフリカとメラネシアの部族が使う「弓の形状」の比較を行なった際、弓の断面がどちらの地域でも、半円形をしていることに気づいた。類似の形態がこのような隔たった地域に存在するという、不思議な事実を発見した。
弓の形状の類似は、弓の材料の性質から必然的に生じたものではなかったため、ラッツェルは「その類似は、発生上の歴史的連関を意味する」という基準を適用した。これを「形態基準(けいたいきじゅん)」という。
つまり、「離れた地域で同じ弓の形状を持つことは、弓の材質が原因なのではなく、アフリカとメラネシアの両地域で同じ文化が共有されているからだ」、という仮説をラッツェルは立てたのである。
離れた別々の地域で、文化の借用と電波が行なわれた。これを歴史的連関という。この事実をラッツェルは「地理的方法、ジェオグラフィック・メソッド(geographic method)」という方法で発見した。これは調査対象である文化の分布を地図上に記入して、伝播経路を推定する方法である(『文化人類学事典』 四三六ページ)。「文化伝播マップ」を作る作業である。
ラッツェルの調査を始まりとして、新しい文化人類学のグループが形成され始める。彼らは一九世紀の進化主義を捨て、「バラバラに生まれた少数の古代文化の中心地、文明から、現存する文化が列を成して発展してきたのだ」という進化論に並ぶ大理論を打ち立てた(ブリタニカ 三二九ページ)。彼らドイツ・オーストリアの研究グループを「グランド・ディフージョニスト」という。
フロベニウスの「文化圏」―クルチュクライゼ・スクール
ラッツェルの弟子レオ・フロベニウス(Leo Frobenius、一八七三〜一九三八年)は、文化を生み出した「文化の中心地」のことを「クルチュルクライゼ(Kultrukreise)」と名づけた。これは「文化圏」という新しい概念である。英語では「カルチュラル・クラスターズ(Cultural Clusters)」という。

フロベニウス
ドイツ・オーストリアの研究グループは「文化圏学派」(クルチュルクライゼ・スクール)とも呼ばれた。
フロベニウスは文化の発生上の連関は、武器といった個々の文化要素にとどまるものではなく、経済・社会・衣食住・信仰といった、人間生活の主要な文化要素の前面に渡って、同時的に見出されるのだと指摘した。フロベニウスは、文化の全ての側面から比較研究しようと提唱したのである。これが「文化圏」の意味である。(『文化人類学事典』 四三四ページ)
「文化圏」とは、ラッツェルの「形態基準」を量的に証明するための手段であった。
個々の文化要素の比較だけではなく、比較が可能な類似した文化要素の数が多ければ多いほど、二つの地域の歴史的連関は、いっそう確実視されるという基準が適応されたのである。これを「量的基準」という。
フロベニウスの「文化圏」という概念を導入して、文化人類学独自の方法論を模索したのがフリッツ・グレーブナー(一八七七〜一九三四年)である。
フロベニウスもラッツェルも、文化圏をあくまで現在にとどまる空間として、静的な把握にとどまっていた。グレーブナーは文化圏に時間的要素を導入する。
グレープナーは文化圏を時間的な新旧前後の関係に還元して、時間的系列の単位として層位化した。これを「文化層」(クルチュルシヒテン)という。
文化層は、ウィーン大学のシュミットによって方法論的基準が確立された。『文化人類学事典』四三五ページにそのことが詳しく書かれていますが、実に分かりにくいので噛み砕いて言います。
文化の「静的な」把握とか、「時間的要素」というのは、古い文化と新しい文化を比べるということである。
二つの文化のどちらがより新しいか、ということは、社会進化論的にどちらが優れた文化で、文明段階に近いかを比較して調べてみるという試みである。
「文化圏」というのは、二つ以上の文化に類似した要素がいくつかあった場合、一つ一つを比較して行き、量的に多ければ多いほど、二つの文化は同一の文化圏に所属していると考えることである。
そうして一つの文化圏として、いくつかの文化圏が確定してくる。これらが文化の発生の中心地であり、それこそが文明であるとするものである。
こうしていくつかの文化圏で類似の文化をまとめた後、異なった文化圏が見えてくる。これらの異なる文化圏を今度は対照させ(というのはどこが違うかを見る、相違点、コントラストを調べるということ)、時間的にどちらのほうが先で、どちらが後に発生したものであるかを調べるのである。この考えを主張したのがグレーブナーで、その方法論を確立したのがシュミットである。
シュミットによれば、他の文化と交わっていない純粋な文化圏のほうが古く、混合した文化圏のほうが新しい。交わっている文化圏の場合、融合度の高いもののほうが古い。一つの文化圏が他の文化圏を切断した場合、切断したほうが新しい。つまり侵略されたり、飲み込まれたりした文化圏のほうが古いということである。
超伝播主義はもともと、イギリス・マンチェスターの解剖学者エリオット・スミス(Eliot Smith)や考古学者ウィリアム・ペリー(William Perry)らの、エジプト研究によって開始された。
二人はエジプトのミイラの解剖の研究や、エジプトの太陽信仰の調査を通じて、「エジプトこそは地球上の文明の唯一の源泉である」と主張した。
エジプトが単一の文明の源であるという学説は、一時はヨーロッパ中に大きな反響を巻き起こしたが、エジプトに伝播の源泉を求めることの出来ない、数多くの文化の存在が確認されたことなどから、現在は学問的に問題外とされている。『文化人類学事典』 四三三ページ)
人間の知的斉一性をもとにした、一九世紀の二つの巨大な仮説は、二〇世紀、アメリカとフランスの大勢の学者たちが、実際に現地に赴いて事実の集積を行ない始めると、批判にさらされることになる。
アメリカ歴史学派―文化相対主義
この学派の代表はフランツ・ボアズ(Franz Boaz、一八五八〜一九四二年)である。文化人類学はアメリカの社会進化理論から始まったが、これに初めて異論を唱えたのがボアズなのである。

ボアズ
文化人類学はフランク・ボアズから社会進化論を離れ、現在のフィールド・ワーク主流の研究方法へと進んでいく。
ボアズは、バッフィンランドのエスキモーや、アメリカ北西部海岸(現在のカナダ、ブリティッシュ・コロンビア)の先住民クワトキルの調査をした経験から、社会進化理論の採用した単線的、リニアーな進化のとらえ方を批判するようになった。
ボアズによれば「個々の文化は、環境との関係や移住の経験、隣接する他の文化からの借用など、それぞれの固有の歴史の積み重ねによって形成されるもので、単純に進化の図式に位置づけられることは出来ない」とするものであった。(『文化人類学20の理論』 五七ページ)
ボアズは複雑多岐に渡る文化現象を取り扱うには、一定の地理、歴史的地域に限定して、言語学、形質人類学(フィジカル・アンスロポロジー physical anthropology)、考古学(archeology)―これらは全て、アンスロポロジーの同じ範疇に入る分野である―の方法論を適用し、文化発展の動態(これを静態=スタティック staticに対して、ダイナミック dynamicという)を統合的に調査するべきであると考えた。
文化を統合的にとらえるためには、社会進化理論が提示した「人間の知的斉一性」や「単線的進化」のような、ある前提を置いてそれに適合するように、後から事実を当てはめるのではなく、まず先に調査された事実から、一般法則を導き出す帰納法が大切であることに気づいた。
ボアズは進化理論を、ばかばかしいものとして初めて非難した人物である。彼が非難したのは、進化論者の研究方法であった。進化論者もまた、コントの提唱したポジティヴィズム(Positivism)の手法で、まず前提を置いてから事実を集積していくという近代的手法を身に付けていた。
しかし、ブリタニカによれば進化論者たちは、事実を自分たちの考えた進化理論のつじつまの合うように選択し、抽象的で分かりにくい進化理論に魅力を添えようとしているとボアズの目に映ったのである。
こうした批判からボアズは、初めてフィールド・ワークを重視する姿勢を打ち出した。これが、多くの若い研究者を奮い立たせたのである。ボアズの業績で最も重要なのは若い研究者を大量に育てたことであろう。
ボアズの弟子には、「文化圏」研究のアルフレッド・グレーブナー、マーガレット・ミード(Margaret Mead)、そして日本研究の草分けの書である『菊と刀』(The Chrysanthemum and the Sword)で有名なルース・ベネディクト(Ruth Benedict)がいる。


ミード ベネディクト
ブリタニカにはボアズが弟子たちに指示したことが端的に書かれている。「研究室に閉じこもっていないで、現地の人々に交わり、同じ生活環境の中で生活を共にして、その民族の人物の行動がどのようなものであるかを証明する事実をつかんで来い。危険を冒してでも現地に赴いて、事実、ファクツと、人々の作り上げた実物、アーティファクツを収集して来い。もし観測が可能なら、それらを文化の過程として記録せよ」
ブリタニカに示されたこの研究姿勢こそ、今日の社会学問系研究者の主流であろう。アフリカのチンパンジーと共に女性研究者が半世紀もの間、アフリカの生息地に滞在したりする。これこそがまさにボアズの遺産である。
ルース・ベネディクトは、彼女にとっての「現地」であった日本に滞在し、実際に日本で生活することで、日本の文化を精密に分析し、克明に記録したのである。
ボアズから始まる「文化歴史学派」は、「文化相対主義」(カルチュラル・レリティヴィズム Cultural Relativism)とも呼ばれるようである。しかし、ブリタニカにも『文化人類学事典』にも、「文化相対主義」を学派として紹介している箇所が見当たらない。
『文化人類学20の理論』(弘文社)という本や『新社会学事典』には、西洋を中心とした進化理論に対する一つの理論として紹介されているが、「文化相対主義」という学派は存在しない。
(つづく)