「0102」 論文 江藤淳著『南州残影』(文春文庫、2001年)を書評します。 古村治彦(ふるむらはるひこ)筆 2010年9月20日
昨日、2010年9月18日、故江藤淳氏の著作『南州残影』を読んでいました。江藤氏は文学評論から政治評論まで幅広く活躍された学者です。政治に関して言うと、平成9年(1997年)3月3日の産経新聞に「帰りなん、いざ―小沢一郎君に与う」という文章を掲載しています。これは、2010年4月に産経新聞社から出版された江藤淳著『小沢君、水沢へ帰りたまえ』に所収されています。この本は産経新聞の反小沢を標榜する社員と屋山太郎という評論家が示し合わせて江藤氏の評論文を適当に選んで作った、反小沢キャンペーン本です。

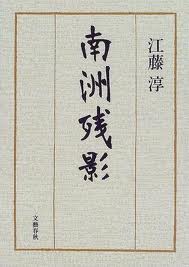

江藤淳 『南州残影』 『小沢君、水沢へ帰りたまえ』
しかし、「帰りなん、いざ―小沢一郎君に与う」という文章で、小沢氏に故郷である水沢市(現・奥州市)に帰ることを江藤氏は提案しています。これは小沢氏の信念をより日本の政界に示すためで、改めて小沢氏の偉大さを知った人々の期待によって小沢氏が中央政界に復帰できると主張した内容です。
屋山太郎は、前書きで、「江藤氏は小沢氏に期待しすぎたのではないか」と、江藤氏のその文意を全く無視した勝手なことを書いています。屋山太郎と産経新聞が江藤氏の意思とは反する形で選集を作り、江藤氏の名前で出して商売をするのは、江藤氏に対する侮辱行為です。売らんかな精神と反小沢キャンペーンが一緒になったものです。最近の小沢氏に関する本の題名がどんどんエスカレートしています。これは麻薬中毒になってしまった人々がもっと刺激を求めて麻薬の種類を変えていくのとよく似ています。

江藤淳と小沢一郎
さて、私が昨日、『南州残影』を読んだのは、私がこれまで自分のブログ(こちらからどうぞ)に何度か書いたように、「小沢氏は西郷ではないか」という思いを持ってきたからです。西郷も小沢氏も「歴史に残る大政治家でありながら悲運の運命を甘受する」点が共通するのではないかと考えています。そして、私は「小沢氏を城山の西郷にするな」という文章を書きました(2010年6月7日「小沢一郎を城山の西郷隆盛にしてはいけない」こちらからどうぞ)。
小沢氏の周囲にいる人間が軽挙妄動して小沢氏の政治生命を危険にさらすようなことをしてはいけない、と書きました。私が「小沢氏は西郷である」と書きましたところ、SNSIの先輩研究員である中田安彦氏が『南州残影』を是非読むようにと薦めてくれました。そこで読んでみました。
この『南州残影』は、西南戦争をテーマとしています。西南戦争とは、明治10年(1877年)に鹿児島に隠遁していた明治維新の三傑の一人である西郷隆盛が鹿児島の士族を引き連れて起こした反乱です。翌年には官軍に追い詰められ、西郷が自刃し西南戦争は終わりました。


西郷隆盛 勝海舟
江藤氏は西郷について書く前に勝海舟についての本を出していました。そして、江藤氏は勝を「政治的人間」と書いています。この政治的人間とは「政治家とは軍人とかいうものは、成功しなければならぬ人々である。もし彼らが失敗すれば、民衆は塗炭の苦しみをなめ、兵士は犬死をしなければならない。だからこそ彼らは成功しなければならず、最後の最後まで努力を傾けて現実の保全を企てようとする」(9ページ)と書いています。勝は旧幕臣たちが西郷側にも新政府側にも与(くみ)しないように金を配り、生活の面倒を見ました。それで大きな勢力である旧幕臣たちを抑え込みました。
政治的人間は目的を達するためならずるいことでも道義に反することでも行う、ということです。そして、江藤氏は政治的人間として成功した勝海舟が逆賊の汚名を着せられ城山で戦死した、失敗した西郷に対して追慕してやまなかったことに疑問を抱き、『南州残影』を書き始めています。
江藤氏は、勝海舟が「現実の保全」に成功した政治的人間であるが、同時に「全的滅亡」を完成させた西郷を追慕する気持ちを、勝海舟が作詞した薩摩琵琶の名曲「城山」を使って分析しています。そして、やはり平家琵琶の名曲「屋島」との対比をさせています。そして、次のように書いています。
(引用はじめ)
政治的人間の役割を離れて、一私人に戻ったとき、海舟の眼に映じたのはこのような光景であったに違いない。平家が亡び、源氏が亡びたあとに浮上したのが、北条執権の武家体制であったように、徳川が亡び、南州と私学校党が亡びたあとには、近代日本というものが樹立されようとしているかに見える。海舟は、政治的人間として、いわばこの近代日本というあり得べき国家に賭けて来たといってもよい。だが、それはいつまでつづくのか。それもまた、やがて滅亡するのではないか。(26ページ)
(引用終わり)
ここで江藤氏は現実の保全に成功した勢力もやがて滅びていくという「亡びへの諦観と憧憬」について書いています。そして、この「亡びへの諦観と憧憬」は江藤氏も共有していたのではないかと私は考えます。江藤氏は『南州残影』の中で様々な資料を使っていますが、それを基にして、西郷の語ったであろう言葉を薩摩訛りで書いています。江藤氏が西郷になりきったと言うよりも憑依したとでも言うべき書き方になっています。江藤氏が薩軍側の言葉を薩摩訛りにしたことで臨場感が高まったと言えます。また、その薩摩訛りは適当な度合いのもので、あまりに薩摩訛りに忠実にしてしまうと分かりにくくなってしまうところを絶妙なバランスを保っていると思います。西郷率いる薩軍は滅びに向かって戦いを始めます。そして、西郷がどうして挙兵したのか。それについて、江藤氏は以下のように書いています。長くなりますが引用します。
(引用はじめ)
私の脳裡には、昭和二十年(一九四五)八月の末日、相模湾を埋め尽くすかと思われた巨大な艦隊の姿が甦って来る。日本の降伏調印を翌々日に控えて、敗者を威圧するために現われた米国太平洋艦隊の?艟(もうどう)である。あれだけ沈めたはずなのに、まだこんなに多くの軍艦が残っていたのかという思いと、これだけの力を相手にして、今まで日本は戦ってきたのかという思いが交錯して、しばしは頭が茫然とした。しかし、だから戦わなければよかったという想いはなかった。こうなることは、最初からわかっていた。だからこそ一所懸命に戦って来たのだと、そのとき小学校六年生の私は思っていた。
その巨大な艦隊の幻影を、ひょっとすると西郷も見ていたのではないか。いくら天に昇って星になったと語り伝えられる西郷でも、未来を予知する能力があったとは思われないというのは、あるいは後世の合理主義者の賢しらごとかもしれない。人間には、あるいは未来予知の能力はないかもしれない。しかし、国の滅亡を予感する能力は与えられているのではないか。その能力が少くとも西郷隆盛にはあり、だからこそ彼は敢えて挙兵したのではなかったか。(50−51ページ)
(引用終わり)
ここで江藤氏は自分と西郷をシンクロさせています。そして、自分が昭和20年、小学校6年で見た風景を西郷も明治の段階で既に見ていたと言うのです。この飛躍力は江藤氏ならではのものであると思います。そして、明治天皇が有栖川宮熾仁(ありすがわのみやたるひと)親王に鹿児島県逆徒征討総督に任じられた時、西郷は鹿児島県令(現在の県知事)からの手紙という形で、今回の挙兵の意図を述べ、「私たちを征討することは正しくない」と暗に明治天皇を批判しています。そして、江藤氏はその時の西郷の心情を次のように書いています。
(引用はじめ)
この「激怒」こそは、純粋な怒りなのだと。その怒りは、国が亡びることへの、国を亡ぼそうとしている者たちへの、人民の怒りなのだと。その怒りを、自分も共有しているからこそ、敢えて出師に及んだのだと。その怒りを、自分も共有しているからこそ、敢えて出師に及んだのだと。そこにはもとより、一片の私心もない。もし、「天子」に歯向い、皇族を叱責することが不忠だとするなら、いかにも陸軍大将西郷隆盛は不忠の臣かも知れない。いや、逆賊ですらあるかも知れない。その汚名は、この際甘受してもよいとしよう。
だが、その「天子」と皇族が、それを戴く政府の「姦謀」が、ともに相寄って自ら国を亡ぼそうとしているとすれば、この一事だけはどうしても赦すことができない。人は一口に、「尽忠報国」という。しかし、「尽忠」ではなくとも、「報国」、即ち国恩に報いずにはいられないという。(57ページ)
(引用終わり)
ここで江藤氏は、西郷を攘夷論者として捉えています。そして、西郷たちは、人民の怒りと共に挙兵したのだとしています。そして、人民の怒りとは、新政府が日本を外国に売り払おうとしているという内容だと言うのです。ここで江藤氏の怒りに満ちた西郷を代弁している部分を引用します。
(引用はじめ)
それでは何故に、「天子」と皇族と政府の輩とが、相集うて国を亡ぼそうとしているといえるのか。彼等こそは兵力と小銃大砲と弾薬と、軍資と糧食と運輸機関と、軍艦と通信電線との力によって、この国を西洋に変えようとしている者たちである。黒船を撃ち攘(はら)い、国を守ることこそ、維新回天の大業の目的だったではないか。しかるに今や、「天子」と皇族と政府の「姦謀」は、自らの手でこの日本の津々浦々に黒船を導き入れ、国土を売り渡そうとしているではないか。西郷はそれが赦せない、しかるが故に立ったのだと。(58ページ)
(引用終わり)
この点について、私は、江藤氏は唐突に西郷を攘夷論者に仕立てていると考えます。その頃、薩摩藩は西洋式の技術を取り入れた軍制改革を行い、戦闘力を高めていました。西洋技術を取り入れるために外国人も招聘していました。そして薩摩藩が洋式技術を取り入れるようになったのは島津斉彬(しまづなりあきら)が藩主になってからです。西郷は島津斉彬に鍛えられ、斉彬に心酔していました。こうした点から西郷が果たして単純な外国を撃ち払えと主張する攘夷論者であったとは私には思えません。西郷は技術を取り入れながら、日本の精神を保全しようという意識はあったのではないかと考えます。

島津斉彬
ここまで江藤氏は、西郷が西南戦争で滅ぶことが分かった上で挙兵した理由を明治維新の目的である攘夷をもはや新政府が、そして攘夷を命令された天子と皇族が捨てて、「日本を西洋諸国」にしようとしていると人民が怒り、その怒りを西郷が共有したからだ、ということを書いています。
西郷率いる(しかし、実際の指揮は篠原国幹、桐野利秋が執っています)薩軍は、「政府へ尋問の廉之有り」で挙兵しているので、本来は東京を目指すか、そこに少しでも近づくことを目的としています。西郷の末弟西郷小兵衛などは「中原(ちゅうげん)」を目指して素早く進軍することを献策しているのですが、実際薩軍は最も拙い策である熊本城包囲を選びます。薩軍を率いる西郷は何も言わず篠原、桐野に任せきりです。彼らは素早く進軍をすることが上策であることなど分かっていたはずです。戊辰戦争で新政府軍を勝利に導いた英雄たちです。創設されてすぐの日本帝国陸海軍の幹部をほんの数年前まで務めていた人物たちです。



篠原国幹 桐野利秋 村田新八
そして、新政府は薩軍の幹部たちの官位剥奪と鹿児島への勅使御差遣を行いました。こうした状況に対して、西郷は、「最初より我等に於ては勝敗を以て論じ候訳にては之無く、元々一つ條理に斃れ候見込の事に付」(83−84ページ)、気になどしないということを、鹿児島県令宛の手紙で書いています。西郷の「條理」について、江藤氏は「むしろ大義というべきものかもしれない。形には見えず、形を滅することによってはじめて顕れるべきもの。それこそ大義の、唯一の形かもしれない」(86ページ)と書いています。

田原坂の激戦
江藤氏は西南戦争の史跡の中でも特に有名な激戦地・田原坂を実際に訪れます。そして、田原坂で地元出身の詩人、蓮田善明(はすだぜんめい)の歌碑を発見するのです。蓮田善明は、学習院中等部時代の三島由紀夫の才能を発見した人物だそうです。そして、応集し南方に派遣され、中尉として終戦を迎えましたが、その直後、上官を通敵行為を理由に射殺し、自分も自決した人物だそうです。江藤氏は、蓮田の歌碑に刻まれた短歌「ふるさとの 驛におりたち 眺めたる かの薄紅葉 忘らえなくに」を見ながら次のような思いに駆られます。

蓮田善明と夫人
(引用はじめ)
「烈火の如き談論風発ぶり」(三島由紀夫「『文藝文化』のころ」)を謳われた蓮田の文学が、何故「ふるさとの驛」の「かの薄紅葉」という表象によって要約されているのだろう。
そう自問したとき、一種雷光のような戦慄が身内を走った。西郷隆盛と蓮田善明と三島由紀夫と、この三者をつなぐものこそ、蓮田の歌碑に刻まれた三十一文字の調べなのではないか。西郷の挙兵も、蓮田や三島の自裁も、みないくばくかは「ふるさとの驛」の、「かの薄紅葉」のためだったのではないだろうか?(103ページ)
(引用終わり)
西郷、三島、蓮田と滅びを選んだ人々を滅びの場である田原坂で思う江藤氏。そこにある歌碑には、優しく、静かな歌が刻まれていなければならないのでしょう。
この『南州残影』には「抜刀隊」という章があります。これは川路利良(かわじとしよし)大警視兼陸軍少将が結成した警視庁抜刀隊のことです。薩軍必殺の剣法である示現流(じげんりゅう)による切り込みに対抗するために士族たちで結成された舞台です。また、抜刀隊の活躍は『抜刀隊』という軍歌にもなりました。のちに陸軍が行進曲として多用し、昭和18年の神宮外苑での学徒出陣の壮行式でも演奏されました。


抜刀隊の図 学徒出陣壮行式
軍歌『抜刀隊』の歌詞は少し奇妙で、西郷と薩軍を讃えていると解釈されても仕方がない部分があります。「敵の大将たる者は 古今無双の英雄で これに従ふつはものは 共に慓悍決死の士 鬼神に恥ぢぬ勇あるも」(147ページ)は一番の歌詞の中にあります。『抜刀隊』は三番まで歌詞がありますが、西郷率いる薩軍を讃える部分がかなりあります。それについて、江藤氏は次のように書いています。
(引用はじめ)
ここにおいて、「西洋」化しているはずの官軍が、却って薩軍の「抜刀隊」に歩兵の理想を見出そうとする倒錯が生じる。同様に、フランスから軍楽隊教師を招き、士気を鼓舞するための行進曲を作曲させているはずの洋式帝国陸軍の理想は、ほかならぬ攘夷の軍隊、「陸軍大将西郷隆盛」を総帥に戴くもう一つの軍隊である。つまり、勝った官軍の理想は、敗けた薩軍にほかならない。(157ページ)
(中略)
しかも、反逆者の軍隊は、昔から「栄えしためし」がないのである。薩軍は敗亡し、西郷は滅亡する。それに憧れ、それを模範とする国軍は、したがって実は敗北と滅亡に憧れる軍隊だと言うことになる。(158ページ)
(引用終わり)
江藤氏は、日本軍に元々備わっている「滅亡への憧憬」を『抜刀隊』の歌詞から喝破しています。これは江藤氏が『南州残影』の最初に書いている、「政治家とは軍人とかいうものは、成功しなければならぬ人々である。もし彼らが失敗すれば、民衆は塗炭の苦しみをなめ、兵士は犬死をしなければならない。だからこそ彼らは成功しなければならず、最後の最後まで努力を傾けて現実の保全を企てようとする」(9ページ)に全く反することです。
西郷率いる薩軍はその後、人吉へと移動します。その移動の困難さを江藤氏は、次のように書いています。
(引用はじめ)
だが、それならこれもまた官軍、いや帝国陸軍によって繰返されることになるあの敗亡と退却の、原型とも言うべき旅程ではないか。
ガダルカナルで、パプアニューギニアで、インパールで、そして比島戦線で、山中彷徨の遠征(アナバシス)は幾度となく繰返された。(173ページ)
(引用終わり)
ここでも、日本帝国陸軍に備わってしまった「滅びの美学」が顔を出します。滅びるまでの過程は辛く、苦しいものであればあるほど、滅びがより美しく感じられます。こう考えていくと、第二次世界大戦の日本側の作戦全体に「滅亡への憧憬」が感じられます。
江藤氏によれば、西郷は元々勝利を得て、実際に東京まで行き、元同僚や部下である政府の重職たちに尋問をすることは望んでいません。江藤氏は次のように書いています。
(引用はじめ)
西郷は桐野の指揮に任せて、拙に戦い、拙に敗れたい。そして、拙に戦い、拙に敗北した結果、そこから浮かび上がって来るものをこそ、西郷挙兵の目的としたい。(185ページ)
(引用終わり)
西郷率いる薩軍は転戦を重ねますが戦局は悪化の一途をたどります。そしてついに薩軍は出発地である鹿児島に帰還します。出発時には万を超えていた将兵たちは既に300名余りに減っていました。彼らは、島津氏の居城、鶴丸城の後ろにそびえる城山に立て篭もりました。官軍は十重二十重に城山の薩軍を包囲しました。そして、包囲軍の長、山縣有朋は西郷の元へ書簡を送り、自裁することを勧奨しました。

西南戦争時の城山
江藤氏は、西郷は「自裁」ではなく、「戦死」したとしています。これについて、江藤氏は次のように書いています。そして、西郷は切腹ではなく、戦死をしなければならなかったとして次のように書いています。
(引用はじめ)
西郷は所詮「壮士輩」にかつがれたのだ、「故旧に篤きの情」にほだされてことここにいたったのだという点では、山県の書簡も、勝海舟の『城山』も、結局は同じことをいっているに過ぎない。だから、西郷は、決して自裁などしないのだ。王師に背き、国民に背いて数万人の犠牲者を出し、そのことによってのみ天子と国民に尽す道があることを天下に明示するためには、「尋常」に戦死する以外にどんな死に方があるだろうか。(255ページ)
(引用終わり)
官位を奪われ、逆賊となった西郷は、戦死をして首級を敵に与えることによって、大義を示す、国に尽くすことができるのだと考えていたと江藤氏は述べています。
そして、江藤氏は、次のように結論づけています。
(引用はじめ)
このとき実は山県は、自裁せず戦死した西郷南州という強烈な思想と対決していたのである。陽明学でもない、「敬天愛人」ですらない、国粋主義でも、排外思想でもない、それらをすべて超えながら、日本人の心情を深く揺り動かして止まない「西郷南州」という思想。マルクス主義もアナーキズムもそのあらゆる変種も、近代化論もポストモダニズムも、日本人はかつて「西郷南州」以上に強力な思想を一度も持ったことがなかった。(262ページ)
(引用終わり)
「西郷隆盛」ではなく、「西郷南州」という思想。これが、「日本人が到達し得た最高の思想である」、と江藤氏は述べています。それでは「西郷南州」という思想とは何か。それは身を滅して大義を示す、ということなのだろうと私は考えます。
『南州残影』は不思議な本です。膨大な資料にあたって何か新しい事実を発見する歴史書でもなく、空想を膨らませて書いた小説でもありません。ただ、江藤氏の思考がときに西郷と重なり合うことで、西南戦争について新しい視点や解釈を与えてくれる本だと私は考えます。言い換えるなら、江藤氏を憑代(よりしろ)として西郷が「何を考えたのか」を明らかにする本です。
江藤氏は西南戦争について、西郷が「人民の怒り」を共有したので挙兵したとしています。その怒りとは、「攘夷を叫んで行った明治維新なのに、政府高官と皇族が一緒になって西洋諸国に国を売り飛ばそうとしている」というものだとしています。「約束が違うではないか」と人々が怒り、西郷もそのためにたとえ天子に弓引く逆賊になってもその大義を示し、後世に残すために「斃れる」のだということです。
江藤氏は、勝海舟についての本も書かれています。その本では政治的人間として「現実の保全」に成功した政治家、勝海舟を描いています。一方、この『南州残影』では、「全的滅亡」によって大義を後世にまで伝えた、「失敗した」政治的人間の西郷を描いています。そして、江藤氏にとっては、浪漫主義的な甘美さを西郷の「全的滅亡」に見ていたのだと私は思います。
西郷が「全的滅亡」によって大義を示し、国家を救おうとしたのは、生物が種の保存のために、自殺行為を行うように命ずる遺伝子を持っていることとよく似ています。西郷の「自殺行為」は、国家保存のための行為であり、日本にはそうした遺伝子のようなものが組み込まれているのではないか、と私は考えます。
最後までお読み頂きありがとうございました。
※『南州残影』を読み、現在の政治状況について考えたことはブログ「古村治彦の酔生夢死日記」に書きました。お読みいただければ幸いです。
(終わり)