「0135」 論文 サイエンス=学問体系の全体像(25) 鴨川光筆 2011年4月10日
●社会学の研究目的は「文明」である
ここからはブリタニカのソシオロジーの章に沿って社会学とは何かを説明していく。
社会学は「ソシオロジー(Sociology)」という。この言葉を作ったのはオーギュスト・コント(August Comte)である。先にも言ったが、社会学のことを「ソーシャル・サイエンス」とは言わない。ソーシャル・サイエンスとは単数形で使うのではなく、ソーシャル・サイエンシズ(Social Sciences)という「諸学問の総称」のことである。「自然科学」に対するいわゆる「社会科学」のことである。社会学はその一部に過ぎない。
では、ソシオロジーの研究領域(研究目的、研究対象)は何か。私の「学問の全体像」の主目的は、「その学問の目的は何か」「その学問を最初に作ったのは誰か」を、子供にでも分かるように一言で言うことである。これが私の「学問の全体像」の他の様々な「学問解説ハウツー本」とは一線を画するところである。
分かったような振りをして、曖昧な、難しそうな言葉を弄して知的さを装う、他のどの学問の偽善的解説者よりも、私鴨川光が優れているのはこの点である。私の「学問の全体像」を読めば、一通りの世界レベルの共有知識を獲得出来るのです。
はっきり言う。社会学の研究目的は「文明」(シヴィライゼイション civilization)である。人間が作った「文明とは何か」を突き詰めることである。詳しく言うと、「文明の源と発達、文明がもたらした制度(インスティチューションズ institututions)を研究すること」である。
(著者注記:これを下に引用するウィキペディアの「社会学」の項の冒頭説明と比べてみよ。)
(引用はじめ)
社会学(しゃかいがく、英: sociology)は、社会現象の実態や、現象の起こる原因に関するメカニズム(因果関係)を解明するための学問である。その研究対象は、行為、行動、相互作用といったミクロレベルのものから、家族、コミュニティなどの集団、組織、さらには、社会構造やその変動(社会変動)などマクロレベルに及ぶものまでさまざまである。思想史的に言えば、「同時代(史)を把握する認識・概念(コンセプト)」を作り出そうとする学問である。(ウィキペディア「社会学」から引用)
(引用終わり)
わかったようなことをいうな。冒頭から「その研究対象は〜さまざまである」などとよく言えたものである。経済学ならば「お金のこと」であるとか、政治学なら「国のこと」ということぐらい、誰にでも言えるであろう。ある一つの研究対象があるから、ある一つのサイエンスがあるというのに。
上記のウィキペディアの引用部分である「社会現象の実態や、現象の起こる原因に関するメカニズム(因果関係)を解明するための学問である」というところは、文中の「社会」を「自然」に代えただけで、「自然科学」(ナチュラル・サイエンシズ Natural Sciences)の説明になるではないか。つまり上記のウィキペディアの説明は「社会科学」(ソーシャル・サイエンシズ)の説明なのであって、社会学それ自体の説明には全くなっていない。
「政治学」の項を読むと、その冒頭では「政治学は、政治を対象とする学問分野」などと書かれている。ナメてんのか。
これが「分かったような振りをして、曖昧な、難しそうな言葉を弄して知的さを装う、他のどの学問の偽善的解説」だと私が言う部分なのである。これはウィキペディアだけの問題ではない。
●「学問の全体像」ここまでの整理
ここで一回整理しておこう。
これまで私が学問をどのように整理してきたかを述べておきます。その学問の研究目的、その学問の開始となった人物、そして近代学問にした人物をさっと書いておく。
(一)自然学問(ナチュラル・サイエンス)
1・物理学―「空間」を研究する。コペルニクスから始まり、ニュートンで近代学問になる。


コペルニクス ニュートン
2・化学―「物質」を研究する。プリーストリから始まり、ラボアジェで近代学問になる。物理学の双子の兄弟。


プリーストリ ラボアジェ
3・医学生理学―「人体」を研究する。ヴェサリウスから始まり、ハーヴィーで近代学問になる。


ヴェサリウス ハーヴィー
4・生物学―「生物(と生態系=エコシステム)」を研究する。リンネから始まり、ダーウィンで近代学問となる。

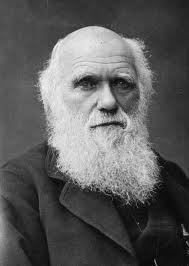
リンネ ダーウィン
ここまではどのような本にも書かれている。ただし物理学の研究目的を「空間である」と言ったのは副島隆彦氏の卓見である。
(二)社会学問(ソーシャル・サイエンス)
1・経済学―「価格」(プライス)を研究する。アダム・スミスから始まり、ワルラスで近代学問となる(七割方)。


スミス ワルラス
2・政治学―「主権」(ソーヴリィンティ)を研究する。マキャベリから始まり、アーサー・ベントレーで近代学問となる(一応)。

マキャベリ
3・人類学(文化人類学)―人間の中の「民族」(という言葉は本当は使えず、正しくはエスニシティ ethnicity)を研究する。エドワード・タイラーから始まり、レヴィ=ストロースで近代学問となる(一応)。


タイラー レヴィ=ストロース
あとの二つ、社会学と心理学はこれから書きます。
この中で、政治学の研究目的が「主権」(ソーヴリィンティ)であることと、経済学が「価格」(プライス)であることを、私、鴨川はブリタニカで見出した。小室直樹氏は政治学の目的を「資本主義」、副島隆彦氏は政治学の目的を「統治」(レイン、reign)と述べている。この説明ではまだ曖昧である。
(著者注記:この「主権」(ソーヴリィン)と「統治」(レイン)という言葉の違いをいつか説明しなければならない。今ここでいえることは、この二つの言葉は、語源と意味が共に同じものである。ほぼ同じ言葉であろう。私のこの「学問の全体像」は、副島氏や小室直樹博士の業績の追試、テスティフィケーション testificationとしての役目を果たしている。)
経済学に関して言えば、小室氏の言う「資本主義」だけでは「お金の値段って、どうしてつくの?」という、子供のもつ素朴な質問には答えられない。政治学に関しても、副島氏の「統治」では「国って誰が作ったの?」という質問には答えられない。この答えをもっと簡潔に推し進めたのが私、鴨川光ということになる。
●社会学とは「人間行動の学問」と定義されているが
社会学の話に戻ろう。社会学が行なう文明の研究とはどのようにして行なうのか。ここから退屈な内容になりますが、なるべく簡潔に説明するので、どうかついて来てください。
ブリタニカによれば文明の研究方法は二つある。一つは静態的研究(スタティック・アプローチ static approach)、もう一つは動態的研究(ダイナミック・アプローチ dynamic approach)という。
静態的研究とは、社会の秩序が「形成される過程」を調べることであり、動態的研究とは社会進化論的「変化の過程」を調べることである。
オーギュスト・コントもハーバート・スペンサー(Herbert Spencer)も、世界に現存する全ての社会は、ヨーロッパが何万年もかけて経験してきた、発展段階の過程にいる姿であると信じていた。


コント スペンサー
文化人類学のところで私が述べたとおり、このブリタニカの記述は、一九世紀の社会学者の態度である。コントは社会学の生みの親であり、ハーバート・スペンサーは社会進化論(Social Evolution Theory)の生みの親である。両者共に、社会学の研究目的は「文明」であると考えていた。その頂点に立つのが西欧で、全ての人類はヨーロッパと同様の文明の形成に向かって進化を続け、その最終段階に西欧の文明状態がある。そうした前提に立って人類と文明を考えるのが、一九世紀の社会学者の基本的態度だったのである。
また一九世紀当時は、社会学は文化人類学と学問的に明確な線引きがなされていなかった。
政治学のところでも述べたが、コントはサイエンスのヒエラルキーを考案し、そのトップに社会学をすえた。最も下にあるのが最古のサイエンスである天文学。そこから順に、物理学、化学、生物学と上っていって、最も新しく最大のサイエンスが社会学であると考えた。
政治学、経済学、心理学、人類学が無いではないかと思われるだろうが、当時はまだソーシャル・サイエンスは存在していなかった。
(著者注記:いや、大学教育、学部でさえソーシャル・サイエンスを教え始めたのは戦後のことである。これは行動科学を中心にしたアメリカのソーシャル・サイエンティストたちが、自分たちの新しい学問をヨーロッパに対抗して打ちたてたのだと凱歌を上げたという経緯を副島氏は『属国日本論を越えて』などの著作で書いている。それまでの大学教育は、自然科学以外は古典研究だったのだ、ということをベネディクト・アンダーソンが講演録で正直に述べていたことも、前回の文化人類学の中で紹介した。)
●サイエンスの目的は「力」=フォース(force)を発見することである
ソシオロジーの研究目的は文明であると私は言ったが、ブリタニカによれば現在ではその考え方は正確ではない。社会学とは「人間の行動」(ヒューマン・ビヘイヴィアー human behavior)を研究する学問の一つであるとしている。
一般的に「人間行動学」とか「行動科学」などと呼ばれているこの学問は、ブリタニカでは「人間行動の学問」(ザ・サイエンス・オブ・ヒューマン・ビヘイヴィアー the Scinece of Human Behavior)と記述されている。「人間行動の学問」とは「人間社会や、人間同士の交わりの中で生じる因果関係を発見する学問」だと書かれている。
ブリタニカによれば、「人間行動の学問」には、慣習、構造、制度(インスティチューション)や、「集団を結束させたり弱めたりする「力」(パワー=権力ではなく、自然界に存在する力=フォーシズ forces)」や、「集団や組織に関することから生じる人間の行動」、そして「人間の性格へ及ぼす影響」に関する研究が存在する。
これはつまり「人間界に存在する力」「人間の行動」と「それらが人間に及ぼす影響」を研究するものだと言っているのだ。もっと簡単に言えば、社会科学とは、「人間の作った社会に力=フォースは存在するのか」を追求する学問である。
そもそも学問、サイエンスとはこの「フォースの存在追求」のことなのである。これは私が物理学から学問の成立を調べ上げていくうちに達した結論である。動物にはない「ソサエティ(society)」というものを作った「力」とは何なのか。果たしてそのような「力」が存在するのか。社会学とはこの力を見つけることなのである。
例えば経済学の研究対象は「価格」(プライス price)であるといったが、正確には「価格を決定する力(フォース)とは何なのか」を追求することなのである。これははっきりとブリタニカに書かれている。
最終的にはこの「フォースというものが在る」と考えて(あるいはしっかりと発見して)、その「力のつりあい、均衡状態、バランスの取れた状態」を見出すことなのである。
私の学問の全体像をこれまでしっかりと読んで下さっている読者の皆さんなら、この先私が言いたいことがお分かりであろう。そう、「エクィリブリアム・セオリー(Equilibrium Theory)」が打ち立てられることで、その領域が初めてモダーン・サイエンスとしてめでたく成立するのである。であるから、レヴィ・ストロースの「構造主義」が文化人類学をサイエンスとするものである。民族の文化を構造としてとらえ、そこにシステムを発見することである。システムとエクィリブリアムはほぼ同義である。
●それでもやはり社会学の研究対象は「文明」である
では、なぜ人間の行動を調べることが社会学の成立につながっていったのか。
ブリタニカによれば、人間以外の動物の行動は本能によって決定されるが、人間の場合、動物とは違って自分の行動を決定してくれるこの本能が備わっていない。その代わりに人間は社会生活営まなくてはならない。「人間は社会生活をする動物である」というこの事実が人間の行動を決定付ける、と書かれている。
これは誰にでもわかることであろう。馬などの四足動物は、産み落とされたらすぐに立ち上がるが、人間には出来ない。人間の場合、赤ちゃんのハイハイ歩きから親によって学習させられなくてはならない。親、家族という単位が社会学上の最小の「社会」であるということも、この考え方から納得のいくことである。
ブリタニカはそこからさらに論を進めて、「人間は社会組織(ソーシャル・オーガニズム social organism)に頼らなくてはならない動物であり、そのため制度化された社会形態は、人間の活動に大きな影響を与える」と書かれている。
現在の私たちは、人間社会の発達を、家族(ファミリー family)から始まり、部族(トライブ tribe)、村や農村のような共同体(コミュニティ community)、そして都市国家のような社会(ソサエティ society)になったのだと考えている。親子や家族のような自然な人間のつながりから、近隣の人々との助け合いへと言ったように、徐々に大きくなっていったものだと考えているだろう。
最終的に現代のような近代社会に到達し、法制度や政治制度、株式会社と言った諸制度、組織が整った状態の中で生活せざるを得ない。現代の私たちはまさしくそうである。人間は「ソーシャル・オーガニズム」に頼らなくてはならない、とはそのことを言っているのである。
ブリタニカは社会学の研究目的を「社会組織が人間にどのように影響を及ぼしているか、どのように制度化され、発展し、高度化し、相互に作用しあい、衰退し、消滅していくか」と結んでいる。
しかし、これは国家や帝国の盛衰のことにほかならないではないか。だから私鴨川はこう思う。結局オーギュスト・コント、ハーバート・スペンサーの信じていたところが正しい。社会学の研究目的は、やはり「文明」なのである。
人間のつながりがいかにして文明の状態になるのか、それに至る人間同士のつながり、ソサエティを成立させた「力=フォース」とは何かを考える学問なのである。社会を成立させた力が存在するかどうかということがその前に問題になるのだが。
いずれにしろ、ブリタニカを丹念に読めば読むほど「社会学の研究対象は文明である」ということが明らかになった。このことは私鴨川光の発見である。おそらくはどの社会学の教科書にもそうとははっきり書かれていないであろう。
だから私ははっきりと宣言しておきます。社会学の研究対象は「文明」(シヴィライゼイション)であると。
「社会学の研究対象は社会である」などという日本の学者・知識人の人を馬鹿にしたような、頭のたりない解釈はしません。日本版ブリタニカの社会学の章には、はっきりと恥かしげもなくそのように書かれている。「社会学の研究対象は社会である」という書き出しは、大学生の卒業論文レベルである。
西洋人は自分たちが住んでいる文明、シヴィライゼイションがいかにして成立して発達してきたのかを本気で考え心配し、解き明かしたいのである。社会学はそのためのツールとして生まれたのである。
社会学の研究対象、それは「文明である」とはっきり私鴨川は宣言しておきます。後でタルコット・パーソンズ(Talcot Persons)を説明する時に引用するが、社会学の泰斗(たいと)小室直樹博士でさえも、社会学のことをそのようにはっきりとは言っていないでしょう。

パーソンズ
●社会学はフォークロア=民間伝承採集とは違う
引き続きブリタニカを引いた社会学の話に戻ります。社会学は「人間行動の学問」(サイエンス・オブ・ヒューマン・ビヘイヴィァー)の一つである。社会学が研究するものの一つは「構造」(ストラクチャー structure)である。その「構造」、「社会を構造ととらえる考え方がある」ということは、私鴨川が文化人類学のところで説明した(文化人類学者レヴィ・ストロースとラドクリフ・ブラウン構造主義は、社会学でも大活躍する)。
ブリタニカは、構造の中でも社会学にとって、特に重要なのが「家族」であるとしている。これは人間の社会(ソサエティ、人のつながりのこと。これを福沢諭吉は「人間交際」と訳した)が、生まれてから最初に始まるのが家族という最小単位だからであろう。家族以外の「構造」としては、「貴族」(ピアー・グループ peer group)、「共同体」(コミュニティ)、経済政治秩序(エコノミック・ポリティカル・オーダー)や、教会、軍隊などが社会学の扱う集団である。
(著者注記:ここで「集団=グループ」という言葉が出てきたが、社会学は文化人類学から構造が取り入れられるまで、最初に「集団」という考え方が出現した。これが後に政治学に導入され、政治学が学問として一挙に発展していく契機に成ったことを政治学のところで述べた。)
社会学の源流は、ギリシャ哲学に遡ることが出来るが、直接には一八世紀、英仏で生まれた啓蒙思想(エンライテンメント) enlightenmentの子孫である。それまでの社会現象の取り扱いは、古典哲学や民間伝承(フォークロア folkrore、民俗学という)などのような、非学問的アプローチによることばかりであった。社会学はそれに対する反発から生まれたものと言える。
(著者注記:「民俗学」とはフォークロアという。民間伝承と同義で、民話や民謡などがそう。ペルーの音楽をフォルクローレというが、これも全く同じもの。柳田國男、和辻哲郎、金田一京助などが取り組んだ学問。これと民族学は違う。民族学はエスノロジー ethnologyといって、文化人類学のヨーロッパで発達したターミノロジー、用語で、文化人類学と全く同じものである。つまり、「民族学」は一応学問だが「民俗学」は、かつて人間に書き残された文字などを取り扱うこともあるので、本来、ヒューマニティーズ、「人文」の域を出ない。ここのところを読者の皆さん、分かってください。)



柳田國男 和辻哲郎 金田一京助
社会学は「フォークロア」(民間伝承採集。昆虫採集や植物採集などと同じこと。つまり博物学、「ナチュラル・ヒストリーズ Natural Histories」)からの脱却の面があったということなのである。
●社会学はソーシャル・ダーウィニズムから始まった
ブリタニカは「社会学の歴史的発展」と題して、最初に「ソーシャル・ダーウィニズム(Social Darwinism)と進化主義」を取り上げている。
ダーウィニアンズとは進化理論を唱えたダーウィンの信奉者たちのことである。彼らの進化理論によって、「人間行動の学問」は一九世紀末、学術的な地位を確立できる可能性が高まっていったのである。
進化理論とは、一八世紀ぐらいからラマルク(Jean-Baptiste Lamarck)やキュヴィエ(Baron Georges Cuvier)らによって激烈な論争が交わされてきた長い歴史を持つ。決してダーウィンがいきなり作り出したものではない。ダーウィンよりもハーバート・スペンサーのほうが理論を打ち出したのは先である。


ラマルク キュヴィエ
ダーウィニアンズとは文化人類学のところで私が取り上げた、ハーバート・スペンサー、ルイス・モルガン(Lewis Morgan)、エドワード・タイラー(Edward Burnett Tylor)らのことである。
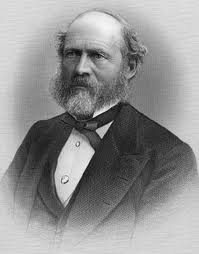
モルガン
ブリタニカの記述によれば、彼らダーウィニアンズ達は、人間社会を生物学的有機体(リヴィング・オーガニズム living oranism)のアナロジーとしてとらえたとある(著者注記:つまり比ゆ、たとえ、人間社会を生物だとたとえたということ)。そして進化理論の要素を社会学に導入した。進化理論の要素は文化人類学のところで述べた社会進化論のことである。
このブリタニカの説明だけでは、何となく「ああ、そういうものか」という感覚だけで終わってしまうであろう。わかったような気持ちになるだけである。
何故、初期の文化人類学者はハーバート・スペンサーの「社会進化理論」(セオリー・オブ・ソーシャル・エヴォリューション Theory of Social Evolution)を取り入れたのか。それは社会の実在を信じていたからである。実在論、存在論の立場にたっているからである。
私鴨川が初期の社会学者、文化人類学者の立場が存在論の立場(社会は単なる人間関係の状態ではなく、物=オブジェクト、事実=ファクツ「=物理的にフィジカルに五感で確認できるもの」が集合体として存在しているという考え)だというのは、社会を有機体として考えていたからである。
社会は存在し、実在し、生物のようなものとして考えれば、そこには当然進化理論が適用できるではないか。当時の学者たちはそう考えたのである。これはフランス革命以前の実質上の社会学の創始者サン・シモン(Saint Simon)から続く、それなりに伝統の長い思想である。
これに決定的な理論的根拠を与えたのが、生物学での進化理論の成功だった。生物学が、一応モダーン・サイエンスとして成功するだろうという観測がダーウィンによって与えられ、これによって文化人類学と社会学にゴーサインが出されたのである。
こう説明すれば、次のブリタニカの説明も府に落ちるところであろう。
「人間社会、文化は、野蛮から未開状態を経て文明に至る。それは弱肉強食(the survival of the fittest)によって達成されるというものだ。」
社会を未開(バーバリアンズ barbarians)から野蛮(サヴェイジズsavages)、最後に文明(シヴィライゼイション)に到達するという、今の我々が当然のように考えていること、この単純なモデルが社会進化理論によって与えられ、文化人類学がテイラーやモルガンによってスタートした。
●「社会」を研究するのは文化人類学の方である、社会学ではない
ブリタニカは次に、社会学と文化人類学の学問的分化の始まりが、一九世紀末に始まったことを述べている。
「そして一九世紀になると、社会学を一つの独立した学問として、心理学、文化人類学、生物学から明確に分離しようと言う声が高まってくる。」
(著者注記:私鴨川はここで補足をしておく。社会学は文化人類学の下にある学問で、もともと両者は一つのものだった。文化人類学は人類学の一角で、その性質上人類学は生物学の影響下にあった。そこで上記にある心理学はどうなのかというと、モダーン・サイエンスという歴史上は、社会学の下に含まれる。厳密に言うと社会心理学が社会学からスタートしている。しかし、心理学はやはり哲学や形而上学と並んで、古代からの古い歴史を持っている。モダーン・サイエンスとして表に出てくるよりもずっと昔から人類の知識として存在し、考えられてきたのである。このことは心理学の時に言わなくてはならないが、それが心理学から社会学が心理学から分離されたという意味なのである。)
なぜ社会学と人類学、同じ「サイエンス・オブ・ヒューマン・ビヘイヴィアー」に学問的線引きが必要になったのか。
生物学からの分離が必要となったのは、「社会有機体理論」そしてこれから出てくる「社会生理学」によって「社会も実在するのだ、その仮説によって進化理論を適用し、生物学が研究する生態系(エコ・システム)とは別に「存在する」ものとして研究しようと考えられてからである。
心理学に関しては後で述べるが、これも人間の心、マインドの研究であることでとりあえずは生物学とは別に研究しなければならないというのはわかると思う。
文化人類学と社会学はなぜ別々に研究されなければならないのか。それは、先にも言った「文明」を研究したかったからである。「文化」とは別のものとして「文明」が如何にして発生したのか。いかにして我々は現在の文明状態に到達したのか。本能による行動が大部分の動物と違い、人間だけがなぜこのような文明状態に至ったのか。その発生原因を知りたかったからである。
ここまで私の学問の全体像を読んでくださった読者の皆様には、もうおわかりであると思う。文化人類学の研究対象(目的、オブジェクト)は「文化、カルチャー」である。これは社会=ソサエティと言い換えても良いのである。それに対して社会学の研究対象は「文明」なのである。人間の「社会」を研究するのは、文化人類学の方なのである。だから「社会学の研究対象は社会である」などという子供騙しの解説、とんちんかんなのである。
日本版ブリタニカの出版元「ティビーエス・ブリタニカ」は無くなっていたのですね
さて、「エンサイクロペイディア・ブリタニカ」でソシオロジーを調べてみたのだが、歴史の部分がどうも短い。デュルケムとタルコット・パーソンズがほとんどである。社会学の基本的な考え方、用語も抽象過ぎてよく分からない。
それで巷に出ている社会学の本を読み漁ってみたのだが、またさらに分からなくなってくる。カッコ付けたくてしょうがない横文字と、いかにも難しそうな専門用語の羅列ばかりである。何を言いたいのか、本人たちにもわかっているのでしょうか。
しょうがないので、日本版ブリタニカを手に取った。書き出しから「社会学の研究対象は社会である」などというふざけた内容に、嘔吐をもようしそうになりながらも、ザーッと見てみた。
(著者注記:私が言う日本版ブリタニカとは「ブリタニカ国際大百科事典」(ティビーエス・ブリタニカ刊)のことである。)
すると社会学の歴史の部分(第八巻、五三〇〜五三五ページ)に、社会学思想の成立の過程が分かりやすくまとめられていたので、それを骨格に、いくつかの社会学の専門書や事典を用いて、エンサイクロペイディア・ブリタニカを肉付けしていく手法をとろうと思います。
日本版ブリタニカによれば「社会学思想は、ヨーロッパ近代初頭以来の啓蒙思想の流れを受け継いでおり、社会学は政治学、経済学と共に啓蒙思想の後継者として出発した」とある。これは正しい。英語版ブリタニカで、私が先に挙げた部分の抜粋である。
(著者注記:日本版ブリタニカに限らず、日本版「NEWSWEEK」も、朝日新聞ら一般紙にしても、外国からの記事は、適当に切り張りして、ところどころを自分たちの勝手な言葉で穴埋めして体裁を整えているだけである。日本語、英語、縦書き、横書き、レイアウトの違いなども原因だが、それでもどこからどこまでが引用なのかがはっきりしないのである。そこでウィキペディアで発行元のTBSブリタニカを調べてみたら、何と日本版「NEWSWEEK」も出していた。TBSブリタニカはもう存在しない会社で、現在は阪急コミュニケーションズといって、TBSはとっくの昔に手を引き、その後サントリーや阪急に買収されていた。ブリタニカの出版は現在ではエンサイクロペイディア・ブリタニカ社が設立した「ブリタニカ・ジャパン」から出版されている。)
さて、日本版ブリタニカによれば、「近代的思想を受け継いだ社会学は、当時最も産業が進み、近代化の進んだ英仏において始まった」とある。これは当然の成り行きであろう。
次回からは、社会学を作り上げてきた人物に焦点を当てていきます。
(つづく)