「0165」 論文 サイエンス=学問体系の全体像(30) 鴨川光(かもがわひろし)筆 2011年11月12日
●サン・シモン主義者

サン・シモン
サン・シモンの死後、彼の思想は、O・ロドリーゴ、B・P・アンファンタン、A・バザールら弟子たちに受け継がれ、彼らは一つの会派を結成した。彼らは後に、サン・シモン主義者と呼ばれる。
彼らは、サン・シモンの学説を広めるために、各地で講演会を開き、一九三〇年代の全ヨーロッパに大きな影響を与えた。サン・シモンが「産業中心の社会」を唱えたように、フランスの高度産業化を推進したのも彼らだった。(「新社会学辞典」 五二四ページ)
それを最もよく表しているのが、一八六七年に催された第二回パリ万博である。当時のフランスは、ナポレオン三世統治下の第二帝政期に当たる。明治維新の年に開かれたこの近代万博は、日本が始めて参加した万博でもあった。
この万博は、巨大な施設や、パビリオン、遊園地、レストランを備えた、現在行なわれているお祭り形式万博の原点であり、「産業の組織化を唱えたサン・シモン主義者であるル・プレが、組織委員長を務めた」。(国会図書館のウェッブ・サイト 「博覧会」から http://www.ndl.go.jp/exposition/s1/1867.html )

パリ万博の様子
サン・シモンの弟子(私鴨川は、この「弟子」という馬鹿みたいな言葉が嫌いで、本当は使いたくない。本来、弟子という場合「ピュピル(pupil)=生徒」と言うしかない)の中の一人、A・バザールは「サン・シモン解義」(一八三〇年)において、サン・シモンまでの思想と、これからの社会建設について上手く要約している。
バザールによれば、歴史は有機的時代と批判的時代の絶えざる交代であるという。
その考え方によれば、有機的時代は共通の信仰によって、社会の統一と安定の気運を生みだす。これに対して、批判的時代には、そのような信仰が存在せず、利己主義が幅を利かせて無政府状態となる。例を挙げると、ソクラテス以前のギリシャは有機的であったが、それ以後は批判の時代であった。
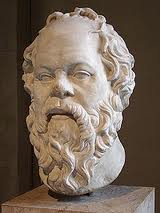
ソクラテス
ローマにおいては、今から二千年前まで、共和国であったころは有機的時代であり、初の皇帝であるアウグストゥスまでが登場し、帝国になった後のローマは批判的時代である。中世の時代はキリスト教によって、有機的時代が始まった。これが一六世紀の宗教改革で解体され、批判的時代が始まる。
サン・シモンの生きた一九世紀初頭は、社会の諸制度を再建し、新しい信仰の体系を作り上げる努力をする時代、つまり有機的時代の再建をすべき時代である。
バザールは、今後新たに作り上げられる社会=モダーン・ソサエティは「全人類を包摂する、さらに巨大な総合体を生み出すに違いない」と述べている。(『西洋思想大事典』第二巻、六一七ページ、「進歩の観念」から)
政治、ポリティクスの実在ではなくて、「社会は実在するのだ」と叫んだところに、サン・シモンの一九世紀的思想の新しさがある。「社会は存在する」という考えを立証するために「社会有機体説(しゃかいゆうきたいせつ)」という、新しい考えが生まれたのだ。
社会は存在し、生命や人体と同じなのだからという前提をもとに、サン・シモンは「社会生理学」という思想を打ち立てたのである。
●オーギュスト・コントの「社会有機体論」
社会学―ソシオロジー(Sociology)―という言葉を作ったのは、サン・シモンの弟子、オーギュスト・コント(August Comte)である。サン・シモンとコントのどちらが創始者かという議論があるが、こう考えればよい。社会学とは、サン・シモンが社会学の「行商」をはじめ、コントが「社会学商店」の看板をかけたのだ。

コント
コントはサン・シモンの弟子ではあるが、後、サン・シモンと喧嘩別れをしたため、アンファンタンらサン・シモン主義者といわれるグループには入っていない。
コントはサン・シモンから後の新しい思想を受け継ぎ、全六巻からなる「実証哲学講義」(じっしょうてつがくこうぎ)(一八三〇年〜一八四二年)を著した。これが完結した一八四二年をして、社会学元年と考える。社会学は現在までに、約一七〇年の歴史があることになる。
『社会学概論』(時潮社)の三三ページから、コントの簡単な来歴を紹介しておく。
コントは一七九八年、南フランスのモンペリエ生まれる。一八一四年、パリのエコール・ポリテクニックに入学。自然科学・技術系の学生であったが、革命的雰囲気の濃い学校であったため、ここで百科全書派のコンドルセや、それと相対するもう一方の思想家である、ド・メストールの思想に影響を受けた。この二つが後のコントの思想の土台となる。そして一八一七年、サン・シモンを知ることとなる。
コントは、サン・シモンの「実証=ポジティヴ(positive)」(神ではなく、人間が前提を置く)という考え方と、「社会生理学」に強い影響を受ける。サン・シモンとの関係が終わった後、コントは一八二六年から自宅で実証哲学の公開講義を行う。これが後に六巻に及ぶ『実証哲学講義(Cours de Philosophie Positive)』となる。コントは一八四五年に、クローチルド・ド・ヴォーという女性と知り合うが、彼女は一年半後に他界してしまう。
その後のコントは主情主義となり、「人類教」と名づけた宗教を始める。コントを支え続けた友人にJ・S・ミルがいるが、この思想転向のころから二人の関係も崩れてしまう。一八五七年、コントはパリに没する。
オーギュスト・コントの業績は、ひとえにサン・シモンの社会生理学と、コンドルセの進歩の観念を引き継いだことにある。この二つについては既にサン・シモンのところで述べた。
しかし、私の考えでは、コント自身の本当の業績は、サン・シモンまでに長い歴史を持つ「進歩の観念」に、新しい思想を融合したことである。それを「社会静学」(しゃかいせいがく、ソーシャル・スタティクス Social Statics)という。
サン・シモンが、それまでの思想家と違うのは「フランス革命によって、秩序と安定とを失ったヨーロッパの社会を再組織しようということを、究極の目的と考えた」(『社会学概論』、時潮社、三四ページ)点である。
サン・シモンは「社会」を発見した。この「社会」とは、今で言う「ソサエティ」ではなく、テュルゴーによって壊されたコーヴェイ(農民による無償の道路整備)等を含む、「共同体(コミュニティ community、ゲゼルシャフト Gesellschaft)」である。一般に「アンシャン・レジーム(ancient regime)」と言われている。
サン・シモンは、社会の再建を考え付いたが、その方法については考えていなかった。コントが新しいのは、サン・シモンの社会再建の発想を受け継ぎながら、その具体的方法を考案したことである。その方法が「社会静学(しゃかいせいがく)、ソーシャル・スタティクス(social statics)」なのである。
では、この社会静学という発想が、一体どこから来たのであろうか。テュルゴーらによる「進歩の観念」には、社会再建の思想は無い。それでも、社会静学は、コントの単なる思い付きなどではなかった。
ブリタニカの三二二ページによれば、コントはハーバート・スペンサーとともに、社会学の主要な部門として静学(スタティクス)と、動学(ダイナミクス dynamics)があると宣言している。
有斐閣の「社会学概論」四、五ページには、「コントは人類社会を一つの有機体としてとらえる。これはコンドルセの「進歩」の理念と、ボナールやメストールの「秩序」の理念を総合したもの」とある。
ここに突如、コンドルセ、ボナール、メストールという名前が出てくる。コンドルセと有機体に関しては、私の論考を忍耐強く読んでくださった読者の皆さんは、もうご存知だろうと思います。しかし、ボナールとかメストールという名前が、いきなり出てきてもらっても困ってしまう。
●「社会動学」(ソーシャル・ダイナミクス)とは「進歩の観念」のことである
「社会静学」とは、ブリタニカによれば「社会秩序の過程(processes of order in society)」を研究することとある。
「社会動学」の方は、「社会の革命的変化の過程(processes of evolutionary change in society)をあつかうとある。「革命的変化」とは、言い換えれば「進歩」のことである。(『社会学概論』、時潮社、三六ページ;『新社会学辞典』、有斐閣、四〇二ページ)
「革命的変化、プロセス・オブ・エヴォリューショナリー・チャンジ・イン・ソサエティ」とは「プログレス・オブ・ソサエティ(progress of society)」、「社会の進歩」と言い換えられるのだ。今では、技術革新のことについて言われ、イノヴェーション(innovation)という言葉になっている。
読者の皆さんはもうお分かりだと思う。「社会動学」とは、コントがコンドルセから受け継いだ「進歩の思想」のことである。
コントは百科全書派から、この思想を体系的理論にして「ソーシャル・ダイナミクス」と名づけたのである。社会の進歩を説明するためにコントは、コンドルセから続く進歩の思想、具体的にはテュルゴーの思想から、ほぼそのままの内容を借り受けた。
そして『実証哲学講義』第四巻五一講で、あの有名な「三段階の法則」を唱えたのである。これに関してはすでに政治学のところで述べている。
三段階の法則とは、「ロワ・デ・トロワ・エタ(loi des trois etats)といい、英語では「ロー・オブ・ザ・スリー・ステイツ(law of the three states)」となる。フランス語の「エタ」とは、英語の「ステイト」=状態となるので、「三状態の法則」とも呼ばれている。むしろその方が、本来の意味に忠実であろう。
コントの社会動学とは、「進歩の観念」のことである。モンテスキュー、パスカルから始まる思想である。おおもとは、デカルトであり、合理主義、ラショナリズムの一派である。だからテュルゴーは、重農主義者(フィジオクラット、physiocrats)であったけれども、かなりリベラルな古典主義経済を推し進めたのである。
「社会動学」「三段階の法則」とは、もとはコントの先人たちの改革思想であり、テュルゴーの改革とフランス革命で実現した「社会の解体思想」なのである。「革命的変化」「チェンジ」とは、社会解体に他ならない。
これで、一九九三年に所信表明演説をおこなったビル・クリントンが、当時なぜ「リフォーム(reform)」という言葉を使ったのかが分かるであろう。「リフォーム」とは、ハウス・リフォームのように、「改良」「改善」することなのである。家を壊して立て替えるのではなく、内装や外壁を作り変える。
「チェンジ」とは、その言葉自体が破壊、解体を意味するのである。家の建て替えである。バラク・オバマの場合、「チェンジ」が彼の代名詞のようになっているが、その言葉の本質は「アメリカの解体」なのである。「革命」「革新」「変化」「解体」は全て同じ意味なのである。
「社会動学」が、破壊の思想の側であることは分かった。では、コントにとって、サン・シモンが考えたヨーロッパ社会の再組織、再建のためには何が必要だったのであろうか。
●コントの「社会静学」とはロマンティシズムのことである
革命によって崩壊したのは、コーヴェイやメチエ(パリでの宣誓ギルドのこと)のような制度だけではなかった。個人の内面にも混乱が起こったのである。今では当然のことだと思われるし、これをアキュート・アノミー(acute anomine)と言ってしまえば話は早いが、これを唱えたデュルケム(一八五八年生まれ)は、まだ歴史に登場していない。
個人の内面の混乱が起こったのは、キリスト教神学、カトリシズムといった、それまでヨーロッパの人と心を長い間つないできた、「クリスティアニティ(Christianity)」(キリスト教徒であること、キリスト教信仰)というヨーロッパの伝統が崩壊したことが原因だった。「進歩の観念」が破壊したのは制度だけに留まらない。制度と共に、人間同士の絆(きずな)も解体されてしまったのである。
コントの「社会静学」の正体は、実はこのキリスト教神学、シオロジー(theology)のことである。コントによる社会再建の試みとは、本質的にキリスト教信仰、カトリシズムの復活なのである。
社会学を構成する「静学」(スタティクス)と「動学」(ダイナミクス)とは、このように互いに全く相容れない二つの思想である。
まずは、社会静学そのものの内容を見ていこう。時潮社の「社会学概論」には、「進歩の観念」によって破壊された後の、社会再建の基礎となる思想が書かれている。
(引用開始)
コントは、家族を社会の真の単位と考えている。人間は家族によってのみ、初めて自我を離れ、かつ自己の最も強烈な本能を抑制することによって、社会生活の原理を学ぶことが出来る。
家族に関係した社会学理論は何を取り扱うかといえば、コントによると、両性の従属関係と年齢の従属関係である。前者は家族を創設するものであり、後者は家族を持続させるのである。
ここで注意しなければならぬ問題は、社会における婦人の地位であるが、コントは男子の地位が優れているという認識を持っていた。(中略)
コントは家族の特質を明らかにしたが、これは社会の原初的自然模型を示すものであった。(『社会学概論』、時潮社、三七ページ)
(引用終わり)
ここに、後の社会学と文化人類学の基盤となる考えがある。コントは「家族」をもって、社会の最も基礎となる単位と考えた。この「家族」という社会を支えるのは何か。
家族を結びつけるものとはコントによれば、男女と年齢の長幼(ちょうよう)による従属関係であった。(同書、三七ページ)
この点に関してコントは、女性に対して男性の優位という考えを持っていたため、ジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill)と対立し、以後、両者は関係を分かつこととなる。ミルは婦人参政権の主唱者であり、フェミニスト運動の元祖といえる人物である。

ミル
「家族」が社会の最小単位というのは、現在の社会学でもその通りである。我々の生活実感でも当たり前のこことして認識されている。では、家族からさらに大きい「社会」となると、それを成り立たせ、持続させるものとは何なのであろうか。
勘のよい方はもうお分かりであろう。社会を生き物、有機体だと考えれば、それを継続させるものは「機能」(ファンクション function)と「連帯」(ソリダリティ solidarity)である。
(引用開始)
家族に続いて分析したのは社会であった。彼に従うと、社会の存立の条件は、機能分化と連帯であった。社会が専門的に機能を分化すればするほど、各部分間の協同と分化した機能の間の調和、すなわち連帯的事実が明白となる。
この際、社会の諸部分そのものは、それぞれ特有の機能を与えられ、相互に依存関係を保ちながら全体に従属する。(『社会学概論』、時潮社、三七ページ)
(引用終わり)
ここにはっきりと、家族を最小単位として考えられた「社会」の存在条件は、「機能分化と連帯である」と書かれている。「分化」と「連帯」、「バラバラ」と「つながり」という相反する二つのキーワードに、コントの社会静学の本質が述べられている。
「社会動学」が「進歩の観念」、デカルトの合理主義から続く最終形態で、後にハーバート・スペンサー(Herbert Spencer)により「社会進化論」となる。これに対して、「社会静学」のほうは、社会を生き物と考える「社会有機体論」である。

スペンサー
社会有機体であるからこそ、人間のように成長するのだと考えられる「社会進化論」は「社会静学」=有機体理論がなければ成り立たない。
上記の引用には「機能の分化」とある。しかし、これでは一つの生物としての社会を、「ばらばらにしてしまう」という意味になってしまう。「分化」とは、どちらかというと解剖学的言葉で、社会を「機械論」、システムとしてとらえているのではないか、と思えてくる。しかしこれは違う。
「社会が、各々の専門的職業に応じて分化する」とは、人間の内臓一つ一つが、それぞれ違った機能を持って、人体という「一つの全体」に貢献することを言うのだ。
(著者注記:「一つの全体」というこの言葉は、後にエミール・デュルケム Emile Durkheimが使うが、非常に重い言葉だ。全ての社会学学徒はこの言葉を聞いてもやり過ごしてしまうであろう。私は、この言葉の重みを知っている。もともとはプラトン、アリストテレスが使った言葉だ。後に詳説する。)
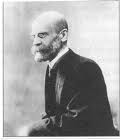
デュルケム
一人ひとりが専門の職業を持って、社会という一つの「有機体」に、機能する=貢献することを言っているのである。だから「連帯、ソリダリティ」という、これまた重みのある、後に、様々な社会運動や、政治運動のスローガンとして使われる言葉が活きてくるのだ。
「連帯」(ソリダリティ、団結とも言う)とは、一人ひとりが専門的機能を有せば有すほど、社会全体に貢献するはずだ。だからバラバラにならず、全員が「社会」という一つの人体、有機体になるのだ。「連帯、ソリダリティ」がそれを解決する。
時潮社の『社会学概論』三八ページに、「相互依存」(そうごいぞん)という言葉があるが、これが各機能、一人ひとりがバラバラにならない理由である。
お互いに依存関係(いぞんかんけい)にある、相関性(そうかんせい)=リレティヴィティ(relativity)、もしくはコーリレイション(correlation)という考えがそこから出てくる。しかし相関性とは、機能理論とは正反対の「構造理論(こうぞうりろん)=システム system、メカニズム mechanism」の側の考え方なのである。生き物とは反対の、「機械、マシーン」の方である。だから後にタルコット・パーソンズの「構造―機能分析」という考えが生まれてくる。
「社会静学」とは以上のことを言う。社会を、生き物、リヴィング・オーガニズム(living organism)だと考える、サン・シモンの社会生理学を受け継いだ考えなのである。
(つづく)