�u�P�W�X�v�@�_���@���{���͓����j�|�������ҁ|�i�R�j�@������i�Ȃ������������j�M�@�Q�O�P�Q�N�T���P�Q��
�����m�̒a��
�@���{�E���q�͂P�P�V�P�N�̓����ȗ��A�Ȃ��Ȃ��D�P���Ȃ��������A�P�P�V�W�N�P�P���A���m�̒��j�E���m�i�Ƃ��ЂƁj���Y�B�s�^�́A���m�ɒj�q�����܂�Ȃ������ꍇ�ɔ����āA���j�E���@�i�ǂ��ق��j�Ƌ�j�E���m�i���傤�ɂ�j�����m�̗P�q�Ƃ��Ă������B����̏ꍇ��z�肵���A���ʌp���҂̗\���ł���B��l�͌��m�̒a����A���̖������I���A�o�Ƃ����B���m�́A���P�Q���ɂ́A�c���q�ɗ��Ă�ꂽ�B
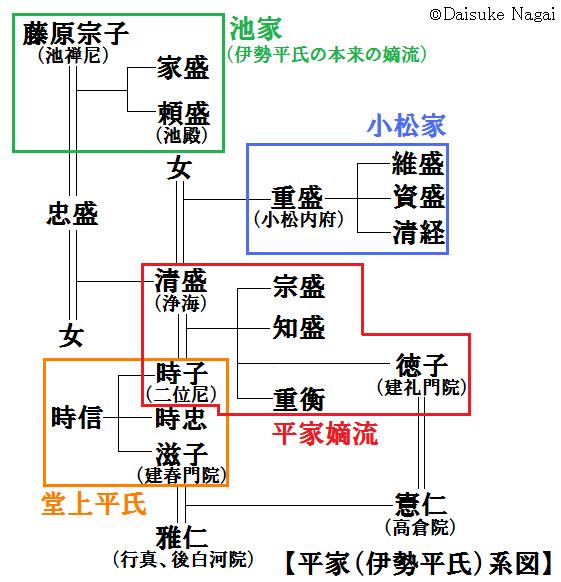
�@���{���i�Ƃ������̂ӁA�c���q�̋���W�j�ɂ͉E��b�E�����������F�C�����������A����b�E�����o�@���C����ꂽ�B�o�@�͗��߂��珢�҂��ꂽ�P�P�U�Q�N�Ȍ�́A��т��ĕ��Ƃɏ]���A�e���Ɣh�����ƂȂ��Ă����B�P�P�V�X�N�Q���A���m�̓�j�E���i���肳���A��͓����B�q�m���˂��n�j�����܂�A���m�����{���C���ꂽ�B���͌��m����܁i�悤���A�����Ɂj�����ꍇ�̗\���Ƃ��ꂽ�B���ʌp���ɂ�����s�^�Ə�C�̘A�g�͈ˑR�Ƃ��āA�Րi�Ⴍ�j�Ȃ��̂ł������B
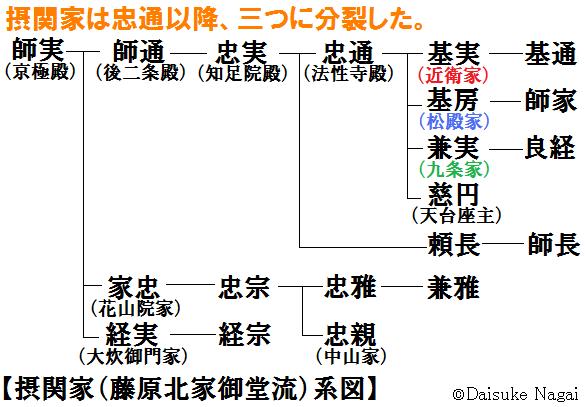
�������O�N����
�@�s�^�͉��ʌp���ł͏�C�ƘA�g�������A�ۊp���ł́A��C���㌩�����ʂł͂Ȃ��A���p���̊�[�����̂܂܁A�ۊ։Ƃ̒����ɂ��Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���悤�ɂȂ��Ă����B�s�^�͊�[�𒄗������邽�߁A�����q�ƌ��������悤�Ƃ�����i��C�̔��œڍ��m�Ƃn�j�A��[�̍Ȃ��c���q�E���m�̗{��Ƃ����肵���B�܂��A��[�̒��j�E�t�Ɓi���낢���j��ۊ։Ƃ̌p���҂Ƃ��Ĉ�Ďn�߂Ă����B
�@�P�P�V�X�N�U���P�V���A�����q�i���͓a�m���炩��ǂ́n�j���Q�S�Ŏ��B���q���������Ă�������̈�Y�́A���m�����q���u�{��v�Ƃ��Ă������Ƃ������Ƃ��āA���m�����������B�s�^�Ɗ�[�͈�U�A���m�ɐۊ։Ɨ̂𑊑������A�t�Ƃ��ۊւɏA�C�����ۂɁA���߂Č��m����t�Ƃɂ�������n�����悤�ƌv�悵�Ă����B�V���Q�X���A���d���i�������{�m���܂Ȃ��Ӂn�j���S�Q�Ŏ��B�ނ́A�ۊp�����ł͊�[�h�ɑ����Ă����B
�@����l���ɂ����āA�t�Ƃ͍s�^�̈ӌ��ɂ��A�}���ɏ��i�������A��ʂ͗�����ꂽ�܂܂ł������B����ɑ��āA��ʂ̌㌩�l�ł����C�́A�@���ɒ���ւ̏o�d�i��������A�o�j�⊯�E�̏A�C�����ۂ����邱�Ƃɂ��A�s�^�ɑ��Ċ�ʂ̏��i�𔗂����i��̓I�ɂ́A�@���ɓ���b�A�C�����ނ����A��ʂ̋N�p�𔗂�j�B�ۊp�����ɂ߂����āA�s�^�Ə�C�̊Ԃɋْ���Ԃ��������A�P�O���A�s�^�͂��ɍŏI������������B
�i���p�J�n�j
�@��������Ԉ�Z������ɂ́A��[�̎q�A���̍������t�Ƃ��A���Ƃ̐�����Q�c���E�����̋߉q��ʂщz���āA�����[���ɔC����ꂽ�B�t�Ƃ͑O�N�܈ʒ����ƂȂ�A���܂܂����[�������ɏA�C�����B���̊����͐ۊ։ƒ����̓����ł���A�����̒n�ʂ��p�������邽�߂ɂƂ�ꂽ�l���ł���B�i���������w�������@�����̖��x�P�W�W�|�P�W�X�y�[�W�j
�i���p�I���j
�@���̐l���ɂ��A�����̐ۊւ͊�ʂł͂Ȃ��A�t�Ƃ��p�����Ƃ��m�肵���B�P�P���P�S���A��C�Ə@�����������琔��R�̌R���𗦂��ē��������B�P�T���A��C�͂܂��A�s�^�Ƃ̌��ɓ������B��C�̍s���ɋ������s�^�́A�ٖ��ɂƂ߁A��C�Ƃ̊W�C����}�����B�ނ̎v���`���Ă�������͂����ł���B�܂��A�s�^���ۊp�����̐ӔC���Ƃ��āA���ނ�\������B���ɁA��C���s�^���ԗ��i����イ�j���A�s�^�����ނ�P��B�����āA�s�^����C�̗v��������A�֔����X�R����B�������āA�s�^�Ə�C�̘a������������B
�@�Ƃ��낪�A�s�^�̎v�킭�͊O�ꂽ�B��C�́A�s�^�̈��ނ���������F�߂��̂ł���B�s�^�̓������ŁA�ۊp�����≄����͖������̂܂܂������B�ۊp�����ŁA�s�^�́u�����v�̊�ʂ����āA�u�T���v�̊�[�E�t�Ƃɐۊւ��p�������悤�Ƃ��Ă����B����ł́A���_��C��A�w�k�i�����ƁA�c���E�M���o�g�̊w��m�j�Ɠ��O�i�ǂ�����A�����[�̑m���A�G�p�W�j�̊ԂōR�����N���Ă����B�s�^���C�������V�����E�o���ɂ́A�m�����܂Ƃ߂�͂��Ȃ������̂ł���B
�@�����̎��Ԃ́A��C���炷��A�s�^�́u�����v�ł������B�s�^�������ɋ��������܂܂ł́A�����̖��͂��܂Ōo���Ă��������Ȃ��B�s�^�����A��蔭���̍����ł���B���������{�I�ɉ������邽�߂ɂ́A�s�^�����ނ����邵���Ȃ��B��C�́A���̂悤�ȍl���Ɏ���A�s�^�̈��ޕ\�������̂܂ܗȏ������̂ł���B���ɏ�C�́A���m�Ƃ̌��ɓ������B��C�͌��m�ɁA�����͍s�^�Ƃ̎�]�W��������������A���q�⌾�m�ƂƂ��ɐ����ֈڏZ����ƍ������B
�@��C�͓��q�ƌ��m���u�l���v�ɂƂ��āA���m�Ɉ��͂��������̂ł���B�Ȏq���u�l���v�ɂƂ�ꂽ���m�͏�C�̗v�����̂݁A��[���֔�����A�t�Ƃ������[�������C���A��ʂ��֔��E����b�E�����҂ɔC�������i�u���m�E��ʐ����v�̔����j�B�P�U���A���_���V�����ɔC�����ꂽ�B���_�����A����Ƃ������܁A��C�����҂����ʂ�A�w�k�Ɠ��O�̘a�����������A����̓����R���͉��������B
�@�P�V���A��b�T�O�l���������ꂽ�B�s�^���߂̉����M���������ɏ���������A�����W�c�i�㗬�M���j�͂قږ����ł���A���̐��͂͂��̂܂܈ێ����ꂽ�B�P�W���A��[�͗��߂ƂȂ�A�Q�O���A�s�^�����H�a�ɗH���ꂽ�B�������ď�C�́u�s�^�E��[�����v��ސw�����A�V���Ɂu���m�E��ʐ����v�𐬗��������B�K�N�i�������j���Ă��玵���ځA��C�͕����ɋA�����B
�@���̐��ς̍ہA�����͍s�^����낤�Ƃ��āA��C�ƑΗ������B�����͍s�^�̑��߂������B��C���R���𗦂��ē��������̂́A�����Ƃ̐퓬��z�肵�Ă̂��Ƃł���B�܂��A�s�^���������ɗ��ꂽ���H�a�Ɋu���i������j�����̂́A�����ƍs�^�̐ڐG�𖢑R�ɐ���߂ł���B��C�͕��͂ŗ������Њd�i�������j�������A��{�I�ɂ́A�����Ƃ̍����������悤�Ɠw�߂Ă���B
�@�P�V���ɉ������ꂽ��b�̒��ɂ͗����̖������������A�����͂����ɕ������Ă���B����́A��C�̗G�a�i�䂤��j�I�Ȏp���������Ă���B�Ȍ�A�����͏�C�ɕ��]����悤�ɂȂ����B��C�����Ƃɂ������āA�������d�������̂́A�ꑰ�̒c���ł������B��C�͍s�^�̎����̈�Ƃ��ĉz�O���i��������̂��Ɂj�m�s����������グ�Ă��邪�A���̗��R�́A����ɗ��Q�W��L����d���̎q�E�ې���ٕ��̋����𖡕��ɂ��邽�߂ł���B
�@��C�́A�V�����̊�Ղ��ł߂邽�߁A�E��b�E���������𐭎��o���Ɍ������ʂ̕⍲���i�V���̌ږ�j�ɋN�p���A�O������b�E�����������[�h�����ʔh�Ɏ�肱�B����ɏ�C�i���Ɓj�A����i�ԎR�@�Ɓj�A�����i����Ɓm�����傤���n�j�A��ʁi�߉q�Ɓm���̂����n�j�̎l�҂������W�Ō���A��ʔh�̒��j���͂��`�����ꂽ�B��C�͉������Ă����������W�c�Ɗ�ʔh���A���m�Ɗ�ʂ̐�����ՂƂ����B�����͌��m�Ɗ�ʂ��Ƃ�A���͂͏@�������������B���m�E��ʐ������A���Ƃ̕��͂�������x����̐��ł���B�V���������̑��d�グ�ɁA�P�P�W�O�N�Q���A���m�����m�i������m����Ƃ��Ă��n�j�ɏ��ʂ��A�s�^�����̉�������B
�@�����O�N���ςƂ͏�C�ɂƂ��āA�����{������ׂ��p�ɖ߂��A����𐳏퉻�����邽�߂̑[�u�������B�s�^�Ə�C�́A���ʌp�����ł́A�u�s�^�\���m�|���m�v�𐳓��Ƃ��邱�Ƃň�v���A�H���Ⴂ�͂Ȃ��������A�ۊp�����ŁA���Ɍ��邱�ƂɂȂ����B��C�ɂƂ��ẮA�s�^���ۊւ���[�E�t�ƂɌp��������悤�Ȏ��Ԃُ͈킾�����B�ނ͊�ʂ̐ۊp������Ƃ��ď��炸�A�Ō�܂ł�����т����B�Ȃ��A�����܂ŏ�C����i�������j�Ȃ��������Ƃ����A���ꂪ�_�X������_�����������炾�B
���㔒�͉@�_

�㔒�͖@�c
�@�����ōs�^�i�㔒�͉@�j�̐l�����ɐG��Ă����B�s�^�͂悭�A�ېg�ɒ��i���j�����d���ƁA�����ǁi�Ă��Ă����j�̘V�ԁi�낤�����j�Ȑl���Ƃ��ĕ`����邪�A���ۂɂ͂��̂悤�Ȑl���ł͂Ȃ������B�ނ͎Ⴂ����́A���ʌp���̌��O�ɂ������߁A�V�c�ɂȂ邽�߂ɕK�v�ȋ�������A�V��ŕ�炵�Ă����B�|�\�ɏ�M��R�₵�A���ɍ��l�i���܂悤�A�̗w�ȁj�ւ̊S�͐��U�s���邱�Ƃ��Ȃ������B�ނ̕��E��o�͍s�^�̂��Ƃ��u���ʂ̊�ʂɂ͂Ȃ��i���ʌp���҂Ƃ��Ă̎������Ȃ��j�v�ƕ]���Ă���B
�@�Ђ��Ȃ��Ƃ��瑦�ʂ��邱�ƂɂȂ������A���̐���͌��l���Ȃ��A�����ۛ��i�т����j�́A�ꓖ��I�Ȃ��̂������B��Ƃ̉i��H�q�i�Ȃ����݂����j�ɂ��A��ǂɂԂ���Ɓu���������͂�߂��v�Ƃ��A�u�����ɊS�����������Ƃ͈�x���Ȃ��v�Ɩ��ӔC�Ȕ��������Ă���i�w�������̐��E�x�Q�O�O�y�[�W�j�B�܂��A�s�^�́A���O�[�����i�̎����傾�ƌ����邪�A���ۂɂ́A�J�b�ƂȂ��Ă͂����Y��A���܂荦�i����j�݂��Ђ����邱�Ƃ��Ȃ��A�M���₷����߂₷���A�J���b�Ƃ������i�������B
�@���ؑחY�i���Ƃ��₷���j�́A�N��̓K���Ɍ�����y���ȐU���i�ӂ�܂��j���A�����O�N���ς���i�Ёj���N�������Ƙ_���Ă���B
�i���p�J�n�j
�@��@�I�ɂ����Ď��X�ɐ��������A���͂̔����ɒ��ʂ���Ƌ������ĕٖ��ɓw�߂�Ƃ����㔒�͂̑ԓx�́A�瑊�ȍD���̊��o�Ɋ�Â����̂ŁA���悻�鉤�ɂ���ł͂Ȃ��B�㔒�͂͐����̕��{�ɐڂ��Ă��A���P�J�����i���p�Ғ��F�������N�����j�ɂ�����o������A��[��ߐb�̏����͂����Ă��A���g�ɑ��Đ����̍U���̖��悪��������Ǝv��Ȃ������̂ł��낤���B���̕ӂ�̌��ʂ��̊Â���A�����I�ȗc�コ������������ƁA�����ɏn�B�����ߐb�̕⍲���Ȃ��A�܂��鉤�w�Ȃ����Ē鉤�ƂȂ����㔒�͂̊낤���ƌ��E��Ɋ���������̂ł���B�i���ؑחY�w�������̓����x�P�R�Q�y�[�W�j
�i���p�I���j
�@�s�^�̐��ǂɂ�����u���ʂ��̊Â��v��u�����I�ȗc�コ�v�́A��C�ɑ���M���ɗR������B�s�^�͏�C�̂��Ƃ�S��i�����j�A�M�����Ă����B�s�^�Ə�C�̂������́A�V�~�����ŁA�o�@�E�ҕ��̑ߕ߂������ė�������n�܂�B�s�^�ɂ́A�Ō�͌��ǁA��C���܂�āA�����̌����ʂ�ɂ��Ă���邾�낤�Ƃ����v�����݂��������B����Ȋy�ϓI�Ȑ��i���A�����O�N���ς��䂫�N�����̂ł���B
�@�M���W�c����̕]�����Ⴂ�B�����̗���̎�m�Ƃ̐��������ł��A��U�D�ʂȗ������ɓ������A���Ǖ������̂́A�l�]���Ȃ��������炾�B����̒N�����A�s�^��V�c�Ƃ��đ��������l�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B����͎����O�N���ςł������������B
�i���p�J�n�j
�@���̐��ςɂ���āA����͉@���̐����獂�q�̐e���̐��ɕς�����B�㔒�͂͋����I�Ɉ��ނ�����ꂽ�̂ł��������A�������A�M���̐����ɑ��锽���͈ӊO�ȂقǏ������B������d���l�Ƃ���������܂蕷����Ȃ��B����͌㔒�͂��l�]�Ɍ����邱�Ƃ̕\��ł��낤�B����ɂƂ��Č㔒�͂ɂ͈��ނ��Ă��炤�����悢�A�Ƃ��镵�͋C���M���ɂ͂���B�����̍s���́A�d���̂Ȃ����ƂƂ��ċM���Ɏx�������ʂ��������B�i�͓��˕�w�V�c�̗��j�O�S�@�V�c�ƒ����̕��m�x�T�W�y�[�W�j
�i���p�I���j
���m�g�j�̑�̓h���}�u�������v�������̕��́A���������Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�@�s�^�́A����̃g���u�����C�J�[���Ǝv���Ă����B���H�a�ɗH���ꂽ�s�^�́A���ɔ��Ȃ����l�q���Ȃ��A���l�O���i����܂��j�̐����𑗂��Ă����B�s�^�́A���ۂɂ͖�����N���A�l�������ȁA���\�Ȑl���������̂ł���B
���Ȑm����
�@�����O�N���ςƂ́A�M���̏��ɓI�Ȏx���āA��C���s�^�E��[������ސw�����������ł������B�m�s�����������Ƃ͂����A���Ƃ̌����̐��͂T�l�ŕς炸�A���Ƃ��̂��̂͂����܂Ő����̉��x���ɓO���A�����͂���܂œ��l�A��c�i���m�j�Ɛې��i��ʁj�ƌ����i�o�@�A�����j�����d�����B���Ƃ́u�R���ƍِ����v�Ȃǐ��������Ă��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���̐��ς��A���Ⴂ���N���āA���Ƃɂ�钩��ɑ���u�R���N�[�E�f�^�v���Ǝv�����҂���������B����̓����m��Ȃ���O�ƕ��m�ł���B
�i���p�J�n�j
�@���Ƃ��ƕ��m���O�ɂƂ��āA�V�c�Ə㗬�M������Ȃ钩��̓����͉����u�₵�����E�ł���A�����ɋN�������Ƃ������I�ɗ����ł���킯���Ȃ������B
�i�����j
�@�㔒�̗͂H�Ƃ��������������m�E��O�́A�����̖d���A�㔒�̖͂��O�Ƃ������Ƃ�e�ՂɊm�M���A�����Ռ������̂ł���B�������A�M���Ɍ��킹��A�������������͑����Ɍ���ł��邱�ƂɂȂ낤���B�������A�㔒�͂Ƃ����l��������̓������m��Ȃ����m�E��O�ɂƂ��ẮA���ꂪ�������R�Ȋm�M�ł������B�i�͓��˕�w�V�c�̗��j�O�S�@�V�c�ƒ����̕��m�x�T�X�|�U�O�y�[�W�j
�i���p�I���j
�@���m���O�ɂƂ��āA�����O�N���ςƂ́A��C�̍s�^�ɑ���d���ł������B�s�^���~���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���́u�ϑz�v�Ɋ�A�ŏ����K�N�����̂͑�O�ł������B�P�P�W�O�N�R���A���鎛��O������⋻�����̑�O�ɓ������Ăт����A�s�^�ƌ��m�̒D�����Ă��B�������A�s�^����O�̌v����@���ɖ\�I�������߁A���̊�Ă͖����ɏI�����B�s�^�ɂ͑�O�̌v�悪��������Ƃ͎v�����A�܂��ނ͏�C�ƓG����C���Ȃ������B
�@�T���P�T���A���m�Ə@���́A�s�^�̎O�j�E�Ȑm�i�R�O�j��y�����i�Ƃ��̂��ɁA���m���j�ւ̗��߂Ƃ��邱�Ƃ����肵�A�c�ЂD�i�͂����j���A�u���Ȍ��i�����Ă�j�v�Ǝ����i�������j���������B�����̗��R�́A�u�����A�d�����N����������Ȃ�����v�Ƃ������̂ł������B�Ȑm�͂��܂��o�Ƃ����A���ʌp���̉\�����c���Ă���A���݂��̂��̂����m�E���m�̉����ɑ��鋺�ЂƂ��ꂽ�B�Ȑm���d�����N�����Ƃ����؋��͂Ȃ��A�ނ͖����������B
�@�s�^�͈Ȑm���o�Ƃ������A�e���ɂ����Ȃ��������A����͈Ȑm�����m����܂����ꍇ�̉��ʌp���̗\���Ƃ������߂ł���B�������A���m�����ʂ��A���m���傪�a���������ƂȂ��ẮA�Ȑm�͂��̖������I���Ă����B�Ȑm���㌩�����q�i�����@�j���A�Ȑm�̉��ʌp�����i��ے肵�Ă���A�s�^���q�͌��m�̌n���𐳓��Ƃ��邱�Ƃň�v���Ă���B
�@�����A�����g�̌����j�i���˂ȁA�������̗P�q�j���Ȑm�̑ߕ߂Ɍ����������A�Ȑm�͂��łɉ��鎛�i���ꌧ��Îs�j�ɓ�������ł����B���鎛��O�͒��삩��̈Ȑm�̈��n�i�Ђ��킽���j�v�������݁A����⋻�����Ɣ����Ɠ������������悤�Ƃ����B
�i���p�J�n�j
�@��J���O�̑�O�ɂ��V�c�U�������������Ȑm�̍s���Ɍ���I�ȉe����^�������Ƃ͊m���ł��낤�B���̎��_�ɂ����āA�����Ɣh�Ƃ��Ċ������Ă����̂͑�O�݂̂ł������B
�@�Ȑm�͂��̑�O�Ɋ�]�����o���A���鎛�ɋ�������B��O�ɉ䂪�g���ςˁA�N����}�����̂ł���B�i�͓��˕�w���{�����̒���E���{�̐��x�Q�O�R�y�[�W�j
�i���p�I���j
�@���Ԃ́A����ƈȐm��i���鉀�鎛�E����E��������O�̑S�ʑΌ��ɔ��W�����B�Q�P���A����͉��鎛�U�������肵�A���Ə����ƌ������ɏo�w���߂��o���B�Ƃ��낪�A�����[��A�˔@�A�����E���j���q�����鎛�ɋ삯���B�����̓G�O���S�́A�����╽�Ƃɑ傫�ȏՌ���^�����B�����ł��闊���i���O�ʓ����m����݂ɂイ�ǂ��n�j�́A�����Ɛ��͂̒��S�ɂȂ肩�˂Ȃ������B
�@�����͂��łɎO�N�O�̎������N�����̎��ɁA���_�������O�ɒD����Ƃ������Ԃ������Ă���B�����āA����A�܂����P�q�̌��j���Ȑm����蓦�����Ƃ������Ԃ��d�˂��B�O�N�O�A�����͖��_��D�悳�ꂽ�ӔC����C�ɉ����������A���x�����A�����͈Ȑm����蓦�������ӔC���瓦��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����͈Ȑm�ߕ߂̐擪�ɗ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����A�����̖{�S�́u���鎛�U���͂��₾�B��肽���Ȃ��v�Ƃ������̂ł������B�܂��Ă�A�����͏o�Ɠ����̐g�ł������B�u���G�v�ɂȂ邱�Ƃ����������ꂽ���낤�B
�@�����͉��鎛�U��������邽�߂ɁA���鎛���ɐQ�Ԃ����̂ł���B�������A���������鎛�ɋ삯���������ɂ��āA�Ȑm�͑�O�̎x�����}���Ɏ����Ă����B�Q�S���A�����O�����_�̐������A�����Ɠ������痣�E�����B�Q�T���A�Ȑm�E���������鎛���o�āA�ޗǂ��߂����ē��������B�Ȃ��A�Ȑm�͑�O�̎x�����������̂��B��O�͎��@���͂����ʼn�����S���Łi�{���͈Ȑm�ł͂Ȃ��A�s�^�ƌ��m��S�����������j�A�����Ɖ^�����N�����肾�����B
�@���ƌR�́u���G�v�ƂȂ邱�Ƃ�����������Ă��邩��A�O����O�̏@���A���ɂ͂�������Ǝ�o�����ł��Ȃ��B���̊ԂɁA���������Ƃ��痣�����A��C�i�������j�����r�����A�s�^��������̂�҂Ƃ������ł���B��O���g�����Ƃ�œ|����̂ł͂Ȃ��B���f�������ɔ���̂ł���B��O����낤�Ƃ��Ă����̂͒���ɑ���u�f���v�ł����āA���ƂƂ́u����v�ł͂Ȃ������B�Ƃ��낪�A�Ȑm�����������ꂽ���Ƃɂ��A���̍��͐��藧���Ȃ��Ȃ����B
�@��O����̐킢�Ȃ�U�����S�O�i���イ����j���镽�ƌR�ł��A���m������Ȃ�Ή��������ɍU�����Ă��邾�낤�B���������ꂽ�Ȑm�̔��f�́A��O�̍���䖳���ɂ����̂ł���B��O�̔M�C�͈�C�ɗ�߂��B�Ȑm�͉��鎛�ɂ����ČǗ����A�����ƂƂ��ɉ��鎛����o�čs������Ȃ��Ȃ����B�Q�U���A�Ȑm�E�����͋������𗊂낤�Ƃ��ēޗǂɌ����������A���̓r���̉F���ŁA���ƕ��Ƃ̐퓬�̖��A�S�ł����B
���m�g�j�̑�̓h���}�u�������v�������̕��́A���������Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�y�Q�l�����z
�@���̕��͂́A������i�Ȃ������������j���͓��˕�i���������傤�����j�̏������y��ɂ��āA�������B���́A�͓��˕�͓��{�����j����Ƃ�����j�w�҂����̒��ŁA�����Ƃ��D��Ă���Ǝv���B�{�����ɖ��������ȊO�̎Q�l�����͈ȉ��̒ʂ�B�͓��˕�w�ی��̗��E�����̗��x�w�����̎���x�^����\�i�݂��킯���j�w�@���x�^�㐙�a�F�i�������������Ђ��j�w�������x�w���j�ɗ���ꂽ���m�@�������x�^���������w���Ƃ̌Q���x�^�|�����O�i���������肼���j�w���{�̗��j�U�@���m�̓o��x�^�����䗴�F�i�����ނ������Ђ��j�w���{�̗��j�O�V�@���m�̐����Ɖ@���x�^Wikipedia�t���[�S�Ȏ��T
�@
�i�I���j