「0103」 論文 サイエンス=学問体系の全体像(22) 鴨川光筆 2010年9月28日
「機能主義」=「ファンクショナリズム」の登場
ボアズによって研究者が実際に現地に赴き、フィールド・ワークを行なうようになった。このボアズの文化人類学の遺産は「文化相対主義」(ぶんかそうたいしゅぎ Cultural Relativism)という。この言葉自体を使ったのは、メルヴィル・J・ハースコヴィッツ(Melville J.Herskovits 一八九五〜一九六三年)である。

ハースコヴィッツ
ところがハースコヴィッツの文化相対主義に関しては、ブリタニカでは一言も述べられていない。『社会学事典』にも『文化人類学事典』を引いても載っていない。ただ『文化人類学二〇の理論』という本だけは詳しく載っている。
ブリタニカでハースコヴィッツは、ボアズの弟子としてだけ紹介されている。文化相対主義は、文化人類学史上では、どの程度の評価であるのかが分からない。
ただボアズは、フィールド・ワークの実践を弟子に伝えたという事実が重要である。後世に残る研究を残した有能な弟子を育てたこと、それがボアズの何よりも優れた業績であろう。
ただしボアズは、社会進化論に代わる文化人類学上の中核となるような思想の導入が必要だと考えていた。
ボアズらアメリカ歴史学者たちは、フィールド・ワークを行なって、現地での観察を通して正確な事実を集積するという、実践行動には優れていた。しかし、事実を体系化するための理論に乏しかったのである。理論によって事実が体系化されなければ学問、サイエンスにはならない。
ボアズは、自らが批判した社会進化論に代わる理論を用意していなかった。理論を批判しながら、新たな理論を打ち立てられないというジレンマに陥ったのである。
ボアズはまとまった著作を残すことはなかった。それでも、ある理論の必要性には気づいていた。それこそが「機能主義」である。機能主義とは「ファンクショナリズム(functionalism)」の訳語で、文化を構成する要素がどのような機能を持っているのかを発見し、理論化することである。
ボアズはフィールド・ワークで集積された事実とは別に、それらを統合する理論として「機能主義」の重要性を考えていたのである。ボアズは「構造主義」と共に、後の社会学問全般を支配することになる「機能主義」の祖となった。
機能主義とは、一九世紀末から二〇世紀にかけて生まれた、」社会学上の大理論である。一言でいうと、社会を「有機体」にたとえて解明していく手段である。有機体とは「オーガニズム(organism)」の訳語である。
「オーガニズム、有機体」とは何か、について説明する
「オーガニズム」、「有機体」とはいったい何か。おそらく読者の大半の方は、正確にはお分かりになっていないであろう。分かっているような、分かっていないような感覚ではないだろうか。「オーガニズム」を「メカニズム」と一緒にしてはいけない。この違いを私は一言で言う。
オーガニズムとは「生命体」のことである。「リヴィング・オーガニズム(living organism)」と言い換えてもいい。私はブリタニカを一〇数年前から読み始めたが、サイエンスの章の「ロマンティック・リヴォルト(romantic revlot)」の項目を読んでいて、この考えの違いに突き当たった。
「ロマンティック・リヴィルト」とは、一八世紀のドイツ・フランスの哲学者(イギリスのナチュラル・フィロソファーに対抗して、ネイチャー・フィロゾファーという。「ロマンティック」というのはイギリス人側からの呼び名である)で、ニュートンらの「メカニクス(mechanics)」(力学、機械論などと言う訳語が当てられている)の大勝利に対抗して沸きあがった、大陸側の学問の潮流である。
そこで私が気づいたのは、どうも西洋思想には、自然界や社会を有機体としてとらえる流れと、無機的な「メカニクス・システム(mechanics system)」としてとらえるという、大きな対立点があるのではないかということだった。
メカニクスとオーガニズムの思想対立は、存在論、オントロギー(ontology)としてとらえることも可能である。
有機体理論は「実在論」の側であり、メカニクスのほうは、「唯名論(nominalism)」につながる思想である。世の中には「力=フォース(force)」以外何も存在しないという思想である。メカニクスのほうが、後の構造主義へとつながっていく。
ブリタニカで「ボアズは、社会をリヴィング・オーガニズムとしてとらえる必要性を説いた」というところを読んで、私の長年の考え、「オーガニズムとメカニクスの対立」という考えは、完全に確かなものとなった。先に述べたハースコヴィッツが重要なのは、このボアズの機能主義を受け継いだところにある。
ボアズは「文化は相対的だ」と唱えたのでは無い―では「レリティヴィティ=相関性(そうかんせい)」とは何か
ハースコヴィッツやボアズは文化相対主義者と呼ばれる。だからと言ってボアズが、「文化というものは、西洋の文明到達点が絶対的なものではなく、たとえアフリカの未開部族の裸と槍の文化であっても、西洋の文明と相対的な価値として計るものだ」と主張したわけではない。
ボアズが文化相対主義者だと言われるのは、実は「機能主義」(きのうしゅぎ)を唱導したからである。「文化相対主義」とは、西洋文明中心主義に対する批判として考えられがちであるが、本当はそうではない。「レリティヴ(relative)」を「相対」と訳してしまったことに、大きな誤解がある。
「レリティヴィズム(Relativism)」は、「レリティヴィティ(relativity)」がもとの言葉で、「相関」(そうかん)」と訳すのが正しい。
「相関」とは、全ての要素がお互いに頼り合い、関連しあって、全体を機能させている、というのが正しい解釈である。
仏教では「相依性(そうえしょう)」という。お互いに頼りあう、「ディペンデンシー(dependency)」で世の中が成り立っている、という思想である。
浄土真宗(じょうどしんしゅう)の開祖、親鸞(しんらん)の「他力本願(たりきほんがん)」も、そこから来ている。互いに「ディペンド(頼る)」から「他力」なのである。
文化人類学の理論はどうしても「構造主義」を必要とする宿命だった
話を戻すと、「全ての要素」ということは、「要素が構成する構造が無くてはならないではないか」と思われる読者の方もおられるであろう。
私鴨川も、「要素が形作るものが必要だ」ということは、結局は「メカニクス・システム(自動的にバランス・オブ・パワー balance of power、エクィリブリアム理論につながる)理論の導入を余儀なくさせるのではないか」と思ったのだが、果たして私の考えは正しかった。
社会の様々な要素が相互に連関して、社会が機能するのだと説明すると、どうしても矛盾が起きる。
「相関理論」は、「オーガン」、「オーガニズム」、「生命体」の側の理論なのである。
機能主義の矛盾を解決するために登場したのが、文化人類学の「構造主義」であり、社会学ではタルコット・パーソンズによる「構造機能主義」(こうぞうきのうしゅぎ)ということになるのである。このことはこの後、レヴィ・ストロースを述べる時に再度説明します。
マリノフスキーとラドクリフ・ブラウン
ボアズの提唱したフィールド・ワークと機能主義によって、文化人類学は新しい時代を迎える。
文化人類学は一九二二年を境に、二つの時代に分けられる。それまでは社会進化理論や超文化伝播主義のような、大仮説を立てることが文化人類学の中心であったが、この年を境にボアズの提唱したフィールド・ワークの実績が本格的に積み上げられていく。
この年、二冊の本が出版される。一冊はブロニスワス・マリノフスキー(Bronis?aw Malinowski)の『西大西洋の遠洋航海者』(Argonauts of the Western Pacific)であり、もう一冊はアルフレッド・ラドクリフ=ブラウン(Alfred Reginald Radcliffe-Brown)の『アンダマン諸島』(The Andaman Islanders)である。


マリノフスキー ラドクリフ=ブラウン
二人は約二年間を南洋諸島で過ごし(行動は別々である。お互い知り合いではない)、フィールド・ワークを行なった(マリノフスキーはニューギニアのトロブリアント諸島、ラドクリフ=ブラウンはベンガル湾のアンダマン諸島)。この頃から文化人類学者の現地滞在は、最低でも約二年間という慣行が生まれる。その結果、それまでの文化人類学者のアプローチであった、ただ仮説を作り出すということに疑問を抱き始める。
それまでの人類学者の仕事は、「諸制度の起源の仮説」を立てたり、「文化史の再構成」を行ったりすることであった。しかし二人は、知られざる過去の再構成に用いられる手法を再検討してみると、証明することが可能な結論に達することが、極めて稀であることに気づく。(『文化人類学事典』 四四〇ページ)
マリノフスキーは、思弁的仮説(しべんてきかせつ、つまり頭で考えただけのもの、想像)による文化史の再構成は、「いかがわしい仕事である」と言い切る。マリノフスキーは、文化の「こま切れ」的扱いに異を唱え、文化を「全体としてとらえる」という新しい試みを提唱し始める。
マリノフスキーの「機能主義」とは、社会を生命体にたとえる伝統的でしかない
「機能主義」とは、文化を「有機的な統合体」としてとらえる理論である。生命体である文化を、さまざまな要素が構成していると考え、個々の要素が、全体としての文化の中で果たす機能を明らかにする。
それを抽象的理論にとどめるのではなく、未開社会における克明な、集中的フィールド・ワークに基づいて、具体的に展開することである。(『文化人類学事典』 四四〇ページ)
マリノフスキーは、「事実を説明する唯一の方法は、機能を定義することである」と述べている。文化人類学の目的は「文化全体として認識すること」であり、「文化を構成する全ての要素が、有機的に関連づいていることを認識すること」である。(ブリタニカ 三二九ページ)。
文化というものは、一つ一つが独自で異なったもの、ユニーク(unique)、ペキュリアー(peculiar)なものである。全ての文化は同一の進化の過程を踏んでいるのだから、比較すればよいという「文化伝播主義」の試みは、無意味であると、マリノフスキーは考えたのである。
同時にマリノフスキーは、歴史的考察も無意味であると考えた。文化はその時点のものとして解釈しなければならない。信頼できる唯一のものは、機能、つまり「今」動いている要素なのである。(ブリタニカ 三二九ページ)
「サヴァイヴァル」という考え方を否定したマリノフスキー
欧米人はサヴァイヴァル(survival)とか、ストロング(strong)という言葉が大好きである。皆さん、外人に使ってみてください。みな一瞬はこちらに振り向いてくれることでしょう。
現在の欧米人の考えるサヴァイヴァルとは、ハーバード・スペンサーの社会進化理論の影響が大きい。

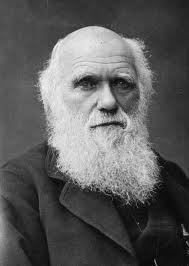
スペンサー ダーウィン
ダーウィンの進化論は、もともとは「ナチュラル・セレクション(natural selection)」という思想だった。「自然淘汰(しぜんとうた)」という訳語が充てられている。スペンサーによって「ナチュラル・セレクション」が「サヴァイヴァル・オブ・ザ・フィッテスト」(適者生存、優勝劣敗 survival of the fittest)という言葉に、勝手に置き換えられたのである。(『文化人類学20の理論』 九ページ)
進化理論を軸にして活動していたそれまでの文化人類学者は、「滅びた文化には何の機能も意味も存在しなかった。機能が依然として働いている文化のみが、生き残ったのだ」と考えていた。
マリノフスキーは「生き残った文化などそもそも存在しない」と反論。「現存する文化には、何らかの機能、ファンクションが備わっているのだ」と主張した。
「ニーズ」という言葉を初めて使ったのがマリノフスキー
マリノフスキーは、人間も結局は動物の一種であり、人類学理論は常に生物学的事実に立脚しなければならないと考えた。そうして導き出したのが「ニーズ(needs)」という考えである。
人間や社会の「機能」とは、個人社会の生命の維持、生存の必要、「生存というニーズ」である。
人間が生存するためには、新陳代謝、運動、休養、健康といった生物学的欲求を満たさねばならないし、人間が社会を営むためには、道具、消費財、観念、技術が必要になってくる。これらをひっくるめて「存在の必要条件」という。
これだけのことを考え出したマリノフスキーであっても、その理論は結局のところ、社会文化を生命体になぞらえること、アナロジー(analogy)による説明でしかない。
アナロジーというのは、一種の「比喩(ひゆ)」である。「たとえること、なぞらえること」である。二つの「似ているもの」の類似点、共通点、「同じようなところ」を見つけ出すことにすぎない。
マリノフスキーは、「ボアズからの流れを踏襲(とうしゅう)」し、「文化を全体として把握する」ために「機能主義」を唱えたが、機能主義の本質は「分析、アナリシス」ではない。アナロジーなのである。
社会や国家の成り立ちを、人間の身体にたとえるという「政治体のアナロジー」の歴史は、古代から存在する。
平凡社の『西洋思想大事典』には「政治体のアナロジー」だけで、一つの章が割かれている。社会の成り立ちを人間の身体にたとえる機能主義は、本質的には政治思想の流れの中にあり、その研究方法は「詩のレトリック=比喩」である。
モダーン・サイエンスの研究の本質は、テクニカル・アナリシスである。分析(アナリシス)と統合(シンセシス)を行なうこと。これが五〇〇年前、ニュートンによって確立された、学問のメソドロジーである。アナロジーでは、どうやっても学問足り得ないのである。
そこにラドクリフ・ブラウンが登場する。ラドクリフ・ブラウンは「機能主義学派」に名を連ねているが、彼の本当の思想は「構造主義」(ストラクチュアリズム)である。
「構造主義」は、社会を生命体として考える機能主義とは異なる。
機能主義は社会を生命として考えるから、本質は「実在論」である。しかし、ラドクリフ・ブラウンは、機能主義から出発したにもかかわらず、「文化は直接観察の対象となるような、具体的実在ではない」と考え、文化を「社会的諸関係の入り組んだ網の目=構造、ストラクチャー」ととらえる必要性を主張した。つまり社会を、一つの体系=システムとしてとらえたのである。(『文化人類学事典』 四四一ページ)
ラドクリフ・ブラウンはボアズの流れを正統に受け継ぎ、フィールド・ワークの実践から機能主義の限界までたどり着いた人物である。ラドクリフ・ブラウンの理論は、レヴィ・ストロースの構造主義に引き継がれていく。
フランスの民族学―エスノロジー
これまでの文化人類学は、ドイツ歴史学派とアメリカのボアズを除いて、ほとんどがイギリスの学者たちの業績である。
イギリスの文化人類学は、社会進化論側からの文化人類学である。しかし、文化人類学は、もともとフランスの社会学から派生した学問である。これこそが本当の人類学の主流であり、現在までの諸学問に多大な影響を与え続けている。
レヴィ・ストロースと構造主義に入る前に、フランスの民族学(エスノロジー)の流れを見ていこう。
フランスの民族学(文化人類学のヨーロッパでの用語法である)は、ヴォルテールの『風習論』やルソーの『人間不平等起源論』(にんげんふびょうどうきげんろん)に源を発する。彼らの思想をサン・シモン、オーギュスト・コントが受け継ぎ、社会学が生まれ、一九世紀から一九三〇年まで、フランス民族学は社会学の時代を経験する。
コントのエンピリカル・ポジティヴィズムを受け継ぎ、社会学を確立したのが、エミール・デュルケム(Emile Durkheim 一八五八〜一九一七年)である。
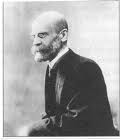
デュルケム
デュルケムは『社会学年報』(しゃかいがくねんぽう)(一八九八〜一九一三年)という機関紙を主催し、社会学と文化人類学の方法論を確立する。デュルケムはどちらかというと社会学者である。一九世紀当時、社会学と文化人類学の明確な区分けはまだ存在しない。
デュルケムが登場するまでにも、ヨーロッパには世界各地の民族、文化、自然に関する大航海時代以来の膨大な資料が蓄積されていた。世界各地に派遣されたイエズス会のミッショナリーや、商人、探検家たちによる資料収集である。
日本でのルイス・フロイス、フランシスコ・ザヴィエル、シーボルトらの活動はよく知られている。しかし結局は旅行者の記録であり、博物学(自然史、ナチュラル・ヒストリーというのが正しい)としての資料が蓄積されただけである。民族に関する研究も、一九世紀までは「民族誌」(エスノグラフィー Ethnography)といった。
デュルケムは、通りすがりの旅行者によって記述された、大雑把な歴史記録に不信を表明し、民族誌にポジティヴィズムを導入する(『文化人類学事典』 四一八ページ)。社会的事実を「物のように」とらえ、客観的考察をすることを提唱した。(『新社会学事典』 有斐閣 一〇四三ページ)
「物のように」とはフランス語で「コム・デ・ショーズ(comme des choses)」といい、英語の「アズ・ザ・シングズ(as the things)」の意味である。
デュルケムの文化人類学的業績を少し述べておくと、『宗教生活の原初形態(The Elementary Forms of Religious Life)』(一九一二年)という著作がそれである。彼はオーストラリアの部族のトーテミズムの研究から、宗教を「世俗なるもの」に対する「聖なるもの」という定義を初めて行なった。
デュルケムは、ロジェ・カイオワ(Roger Caillois)やジョルジュ・バタイユ(Georges Albert Maurice Victor Bataille)といったシュールレアリスト詩人などにも広範に影響を与えている。


カイオワ バタイユ
(つづく)