「0083」 論文 サイエンス=学問体系の全体像(11) 鴨川光筆 2010年5月1日
イギリスの革命は「財産の継承」がその本質である
一六八八年の名誉革命の原理は「権利の宣言、ザ・デクラレーション・オブ・ライツ( the Declaration of Rights)」 であり、国王ウィリアム三世(William III)とメアリー二世(Mary II)がこれを受諾した後、議会が「権利の章典、ザ・ビル・オブ・ライツ(the Bill of Rights)」 として承認した。これをウィリアムとメアリー第一年第二会期法令第二号という。



ウィリアム三世 メアリー二世 「権利の章典」
この宣言は「臣民の権利と自由を宣言して、王冠の継承を確定する法律」である。王族の正統な家系に基づいた「王冠の継承が、臣民の権利と不可分に結びついている」のである。
「権利の宣言」は、臣民の権利だけを宣言したものではない。ましてやプライスの言うような「我々自身の意思で、勝手に王を選んでいいという権利」を宣言したものではない。
「王位の正統と、民の自由を相互に保障した」宣言なのである。権利の章典によってイギリスの国民は、フランス革命にあるような国王選出の権利を子々孫々に至るまで永久に放棄した。

バーク
こうしてみるとバークは保守であり、なぜリベラルであるウィッグ原理の大成者なのだかが一見分からなくなる。どうか混乱しないでほしい。
バークのウィッグ原理は、あくまでトーリー(現在の保守党。当時はロイヤリスト、王党派と呼ばれた)に対抗するためものである。トーリーは国王大権(フィルマーの王権神授説ではない)と国教会の擁護を旗印に掲げていた。これに対してウィッグは民衆の自由と議会の優位を主張した。
バークは伝統の一つとして変革、革命を支持する。本質的には革命主義者である。ただし、変革が合法的であるのは、代議制、リプリゼンタティヴの意見の一致を見た時である。それも憲法の枠内でのみ変革は認められると主張する。(ブリタニカ:マクロペディア 九九六ページ)
議会と憲法を無視した暴力行為で、社会の枠組みと法が一旦壊されると、民衆、ピープルは単なる群集 a mere multitude と化し、権力を握った独裁者の言うがままにされるだけである、こうバークは主張する。
暴力をもって行われた革命は必ずや独裁(dictatorship)に陥る。このバークの洞察は鋭い。ナポレオンに乗っ取られたその後のフランス革命の成り行きや、二〇世紀のヒトラー、ムッソリーニの台頭を見事に言い当てている。
これはバークがアリストテレス(Aristotle)、プラトン(Plato)から続く、政治思想にしっかりと足を据えた知性の持ち主だったからだと言えよう。渡部昇一氏のような「リベ保守」レベルではない。

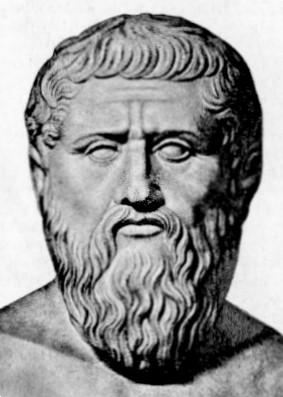
アリストテレス プラトン
それでもたとえヒトラー、ムッソリーニのファシズム(Facsim)が興ろうとも、フランス、ドイツを中心としたヨーロッパはルソーの思想に基づいた社会民主制(Social democracy)、ネオ・コーポラティズム(Neo-Corporatism)に進む決意を固めている。


ヒトラー ムッソリーニ
ヨーロッパは二〇世紀以降、大きくはそのような「理想」へと突き進もうとしているのだ。ただしこれはヨーロッパ全体が大きな監獄となると言うことでもある。私は副島氏から直接そのことを聞いた。このことは後に説明しようと思う。それが「連邦ヨーロッパ」と言う思想(a federal Europe)であり、現在のEUの本質である。
イギリスがいまひとつEUと足並みが揃わないのは、以上のような事情が原因である。国民の自由と王冠の継承を保障した「権利の章典」は、フランスの人権宣言とは本質的に相容れることはない。
それでもイギリスはヨーロッパの一部であり、その流れに逆らう訳にはいかない。だから二〇世紀になるとイギリスではウィッグに成り代わり、労働党(Labor Party)が生まれたのだ。労働党は社会民主制を目指す。
ウィッグ的「リベ保守」思想ではだめなのである
私は高校生の時に世界史を勉強していて、せっかくウィッグ、自由党ができたのにそれが勢力を失って、なぜ共産主義みたいな労働党なんかが台頭したのかが全く分からなかった。
保守党だけが残って、左翼的な労働党が存在し続けるなんて、退行現象なんじゃないのか。その割にイギリスは、世界のどの国よりもリベラルなのはなぜなのだ。実は今の今まで疑問だった。おそらくこの文章をお読みいただいている読者諸氏もそうなのではないか。
私はロック、ルソー、バークを読み解いているうちに、その大きな真実が見えてきた。たとえルソーの思想、人権思想、フランス革命の思想が過激であり、左翼的であり、伝統破壊だと、サッチャーやバークが好きな、渡部昇一氏のような保守言論人が叫んだところでだめなのである。


ロック ルソー
ロック―ウィッグ思想の根本―の思想ではだめなのである。中途半端なのである。アリストテレスから続く西洋の政治思想の課題は、大多数の人間、民衆、ピープルを全て含んだ「民主制実現可能性(feasibility of democracy)の模索である」ということを私鴨川は見抜いた。
ロックの自然権、社会契約説では、都市の住民「シチズン」までしか主権が広がらないのである。ロックの自然権思想では当然、金持ち主体の政策に傾く。これでは古代から続く政治思想上の問題(民主制実現の可能性)の解決につながらない。
歴代の、古代からのあらゆる為政者たちは、民衆、ピープルの不満が一番怖かったのである。だから何とかして、この全ての人間を主権者にした政策を講じてきたが、上手くいかなかったのである。ただの人の、ピープルのわがまま、傲慢さに頭にきて爆発したのが、先に挙げたマキアヴェリの発言である。

マキャベリ
ロックの思想はアリストテレスもすでに述べている。農民や一般ピープルの主権は立法者たる都市住民に預けろと。それが自分たちにとっても一番よいのだと、そう主張したのである。
そのような限界を打ち破った思想がルソーだったのである。ルソーによってシチズンとして古代から知られていた「一般住民でありながら主権者」だった者たちが、「ネイション(nation)」として一般ピープルを包含したまま復活したのである。
ヨーロッパの住民は「ネイション」で進むのである。ロック、ウィッグ思想では「シチズン」までしか主権が広がらない。アリストテレスの「ポリテイア=シティ・ステイト」と何一つ変わらないのである。これでは何の解決にもならない。
ヨーロッパ人は、たとえ自分たちが巨大な監獄の住人であろうとも、主権を持った「ネイション」として生き続け、戦争のない安全な福祉国家として統一されることを望むのである。それほどにヨーロッパは老練であり、戦争、宗教改革、思想対立と言った様々なことを、この五〇〇年間に経験してきたのである。
これがイギリスに労働党が生まれ、ドイツに社会民主党、フランスに社会党が存在している理由である。アメリカで一九世紀に「フェデラリスト(Federalists)」が衰退し、民主党(Democrats)が出来たのも同様の理由である。
本当の保守とは何か
副島氏は本当の保守とは一体何なのか、という疑問に対し、反宗教改革の牙城であるバイエルン(Bayern)を中心とした南ドイツであると述べている。イエズス会以上の筋金入りの反宗教改革の思想であり、ヒトラーもここで生まれている。
私鴨川は、西洋思想の大きな流れの中で考えると、イスラムの正統派こそが本来の保守であると考えている。副島氏も以前そのことに少しだけ触れられている。
このことは私のイスラム、ムータジラ派の文章を読んでみてください。(『副島隆彦の論文教室』 「0005」、「0006」 論文 イスラム研究―ムータジラ派、強欲の思想、つまり理性と信仰を融合させようとした人々(1)(2)。こちらとこちらからどうぞ)
ただし、イギリスを中心にした近代(現代、今の私たちの世につながる)政治思想の流れで言えば、イギリスのトーリーこそが保守である、としていいだろう。あくまで教会と王を擁護するという真の保守である。この点でバーキアンの「永遠の相の下の保守」とは一線を画する。
『フランス革命についての省察』の続きを読む。バークは、プライスの二つ目の主張「彼らの為政者を非行のゆえに放逐する権利」にも反論する。この部分にバークが、実際にはジョン・ロックの思想に基づいた人物であることが露になってくる。
「王をその非行の故に放逐する」と言うのは、人民が主権者として王を下僕と見なすという、本質的に「君主制放棄」の思想である。「人民が放棄する」というのはまさにルソーのジェネラル・ウィルそのものである。
この思想を、イギリス名誉革命に当てはめようとしたプライスに対して、バークは王による「非行」を「いい加減でつかみどころのない見解」だとし、「放逐する権利」を「不確実な原理、実際の運用が困難なものである」と主張している(同書 五五〜五六ページ)。
プライスの主張は、実質的に暴力革命の意思であり、暴力による国家転覆を目指しているととらえられても仕方がない。なぜなら、国王を非行のかどで放逐するためには「武力の行使なしには実現されない」からである(同書 五九ページ)。
では名誉革命の際に、国王ジェームズ二世を退位させた件はどうなるのか、という問題が出てくる。バークはジェームズの退位を定めた法規は、王の非行を理由に定められたのではない、と述べる。
このときの法規には、王は「国民との間の本源的な協約を破壊した」と定められている(五四ページ)。ここにも名誉革命、そしてバークがロックの思想の体現者であることが見て取れる。
バークは「原初契約(original contract)」と言う言葉を使っている(五五ページ)。これこそまさにロックの社会契約論である。国王と国民も、自然法の枠組みの中で、自らの自然権を立法府に預ける、そのように契約したのである。それゆえイギリスの政治制度が代議制による立憲君主制、コンスティチューショナル・モナーキー(constitutional monarchy)として確立したのである。
ジェームズ二世の退位は、この立憲君主制の基本となる社会契約を破棄した結果である、と解釈されたのである。バークは抽象的で形而上学的な思想を嫌うが、それはあくまで、人権思想とジェネラル・ウィルに適用されている。社会契約説には賛成なのである。
最後にプライスの三つ目の主張、「我々の自身のための統治形成の原理」にも反論する。バークのどこを読んでも自然法と言う言葉が見出せず、代わりに「古来」という言葉が出てくるのはこの部分である(六一ページ)。
ここにバークの思想の中心と言える「財産の継承」と言う思想、本音が表れている。バークのオリジナルと言えるのは、ロックの「財産権の保護」から一歩進んだ「財産の継承」という思想である。ここがいわゆるウィッグ的リベラル保守、「リベ保守」が好きなところなのである。
アメリカ共和党的な人々、そしてもちろん渡部昇一氏もこのことを一〇年ほど前に盛んに述べ立ててきた。渡部氏の「相続税は無しにしろ、税率は一律一〇パーセントでいい」と言う主張の元はここにある。
私はこれから「リベ保守」という言葉を使うようにする。これはウィッグに由来したアメリカに影響された日本の「保守論壇ジジイ」のことである。同様に無自覚な二〇、三〇代の若者たちにも多い。「天皇を恭しく思う保守の顔をしたリベラル」なのである。
では九〇年代の日本で優勢となって、一〇数年を経過した「リベ保守(本当はウィッグ)」の思想の本質を述べよう。
「リベ保守」たちの「王位継承」について
先日、小林よしのり氏が『昭和天皇論』を出版した。小林氏の皇位継承問題の核心は「女性に皇位を継承させるか否か」という、いわゆる「女系天皇容認論(じょけいてんのうようにんろん)」である。
現在の皇太子、徳仁親王(なるひとしんのう)に女子がお生まれになったことで、第一子である敬宮愛子内親王(としのみやあいこないしんのう)に帝位を継承させるべきであるか、という議論が巻き起こった。
この議論は、日本のモナーキーである天皇の「継承」という問題に光を当てることになったのだが、二〇〇六年九月、皇太子の弟である秋篠宮文人親王(あきしののみやふみひとしんのう)に男子がお生まれになったことで、「女系天皇容認論」はひとまず立ち消えとなった。
秋篠宮文人親王の第一男子である、悠人親王(ひさひとしんのう)は、皇位継承順位第三位である。秋篠宮は第二位。
なぜこのような議論が起こるのか。それは渡部昇一や桜井よしこ、小堀敬一郎や日本会議といった人々が、男子にのみ皇位を継承させるべきである、という主張を続けているのだが、この主張が依然として根強さを保っているからである。
私は最早、小林よしのり氏を買っていない。氏の優れた分析や、学者が舌を巻くほどの詳細な文献の引用、各地へ足を運んだ取材能力は相変わらず素晴らしい。氏の行動力、分析力、文章力はその画力とともに圧倒的な力を保持し続け、今でもその力に衰えはない。
小林氏は二〇〇二年一一月、産経新聞社の保守論壇誌『正論』誌上で、当時はまだ保守言論人として扱われていた副島隆彦氏と対談を行った。この対談で小林氏は副島氏に圧倒的な敗北を喫したのである。
小林氏はネオコン(Neoconservatives)、ポピュリスト(populists)、グラスルーツ(grassroots)などといった基本的な用語の無知をさらけ出し、近代学問の姿勢をとる副島氏の前で、赤子さながらの幼さをさらけ出してしまった。
私はこの時期は副島氏のことを知らない。むしろ小林ファンだった。この時にも小林氏が「小室直樹の弟子としてデビューした、もと銀行員、シンクタンク研究員を叩きのめすのだろう」程度にしか思っていなかった。
しかし、対談を読んで「小林よしのりが負けた」と思ったのである。私の読者としての当時の素直な感想である。
以後、小林氏は明らかに、副島氏と学問道場を意識した言論活動を行っている。いつだったか『SAPIO』誌上で、連載中の『ゴーマニズム宣言』の中で、「わしのぼやき」という「今日のぼやき」を明らかにパロった内容が載っていたことがある。
二〇一〇年四月には「ゴーマニズム道場」なるウェッブ・サイトを始めるようだが、これは明らかに「学問道場」の真似であろう。
それはそれでいいのだが、二〇〇二年末以降、小林氏は明らかに影響力を持つ副島氏のことを一切触れていない。バツが悪くて無視しているのか、怖いのか、私には分からない。しかし、明らかに影響を受けたふしがありながら、副島氏に一言も触れることがないのはおかしいのである。
私は小林氏の思想は、二〇〇二年以降全く興味がなくなった。ゴーマニズム宣言も、余白の書き込みしか読まない。しかも立ち読みで。いや、最近はそれすらも飛ばし読みをする。たいした視野を持った思想を持っているとは思えない。
小林氏は相変わらす、「パロウキアル・ヴァリュー(parochial value)」の立場でのみ言論活動をしているだけである。「ワールド・ヴァリューズ(世界普遍的価値、world values)」を無視した言論活動をしても、「ウルトラ・ナショナリスト(ultra nationalist)」という「レッテル貼り(レイベリング labelingという)」をされるだけなのである。
小林氏は海外では二〇〇〇年台の早い時期に「ウルトラ・ナショナリスト」というレイベリングをされてしまったのである。
「ナショナリスト」よばれることは「民族指導者」と言うことだから、宗主国、覇権国に恐れられ、警戒される。しかしそれに「ウルトラ」とついたら話が違ってくる。
私個人の体験では、「私は渡部昇一という上智大学の教授の思想が好きです。彼はウルトラ・ナショナリストと呼ばれています」と外国人(この時はケベック人)に話したことがある。その瞬間に座の空気が変わり、私を見る目が一瞬にして変わってしまった。
その場で議論はもう終わり。「ウルトラ」という言葉が出たらもうだめである。これは「ヒトラー」を意味するからである。
同じようにオーストリアの首相ハイダーも「ネオ・ナチ」のようなレイベリングをされて、苦労をしたようである。しかしこれは小林氏とは違う。ハイダーは「ウルトラ・ナショナリスト」などではない。社会民主制を志向した、一八世紀から続く連邦ヨーロッパの思想の体現者である。
小林よしのり砲撃はまた別の機会に行おうと思う。
「王位の継承」と言うことの本当の意味とは「臣民の自由と権利の保障」である
それでも小林氏の「女性天皇を認めるべし」という主張には筋が通っている。
君主、王制の基本、本当の近代の保守思想の基本は「継承」なのである。男系しか認めないなど、「厳格な継承順位」だけに基づいた継承など、本来の君主制ではない。それを支える保守思想にも存在しない。
「継承」の本質は「順位」ではないのである。
少し話がそれるが、ロバート・フィルマーの王権神授説も保守思想ではない。ラディカルな思想の一つである。それまでのどの時代の人間も、王家の系図は神にさかのぼるなどとは言っていない。これは一七世紀の英仏で登場したラディカルな思想なのである。
イギリスの「権利の章典」が規定した王位継承は、男性の王だけに限定してなどいない。男性、女性はおろか、女系であろうとも関係がない。
「権利の章典」に基づいてなされる王冠の継承は、「ジェームズ一世から引き出されたプロテスタントの家系」に限定される。プロテスタントであるというのは、アングリカン・チャーチ、英国国教会を、歩みを一にするからであろうが、それ以外は革命前の王であるジェームズ一世からの系図に基づいて継承される。
これはウィリアムとメアリーの王女である、アン女王から世継ぎが生まれない、と言う見通しに基づいて「王冠の継承と民衆の自由」の保障を、再度確定しなくてはならなくなった時に表面化した。
この時は「臣民が、自らの保護のために、安心して依拠できる王位の継承の確定」(『省察』三七ページ)が急務だったのである。立法府はいっそう綿密に、プロテスタントの家系で、相続すべき顔ぶれの特定にかかった。
名誉革命の時にジェームズ二世は王位から追放され、イギリスの王位が空位になってしまう。この時に作られた「権利の宣言」に基づいて、ジェームズの娘であり、オランダのオレニエ公子ウィリアム(オランダ王、シュターツ・ホルダー)の妻、メアリーに王冠を継承させる。
メアリーは継承順位第一位ではなかった。しかし、近代王位継承法である「権利の宣言」の理念は「臣民の権利と自由を宣言して、王冠の継承を確定する」ことである。厳格な王家の系図に基づいた、王位継承順位を守るための法律ではない。あくまでも「臣民自らの保護のために、安心して依拠できる王位を継承」させることが第一なのである。
言い換えると「権利の章典」は、「国民の自由、権利と不可分に結びついた理念」なのである。これが名誉革命、ウィッグ思想、ロック、バーク、「リベ保守」のリベラルの本質である。「継承」の本質とは、国民の自由、と不可分に結びついた理念なのである。
王の系図を伝承と神話に求めることの前近代=プレ・モダーン(pre-modern)=性
本当の保守、トーリーは、国王の大権(議会によって王権が制限されないこと)と、国教会の維持が、その思想の中心である。彼らは、継承順位や男系にこだわる、といった卑小な考えを持たないし、イングランド王の系図を神にまで求めるという、不可能で愚かな考えも主張しない。イングランド王家のもとはノルマンであり、ヴァイキングである。
イングランド王の系図を、アダムにまで求めようとしたのが、ロバート・フィルマーである。実に大胆で、リベラル以上、ラディカルな思想だということが分かるだろう。王権神授説は本来、保守思想ではない。ましてやアーサー王に系図を求めるような、愚かな人間は昔も今もいない。
これに似ているのが、実は天皇の系図を『古事記』『日本書紀』に求めることである。王家の系図を伝承、伝説に求めることは、ことの是非はどうであれ、「近代、モダーン」ではないのである。
中世以降登場したヨーロッパの王家は、どう頑張ってもローマ帝国時代までしか起源をさかのぼれない。ほとんどは地域の領主であった。
日本の保守が述べるような伝承に系図をさかのぼる試みは、古代ギリシャの王家と同じことをやっているのである。
ギリシャの王家や貴族は、その系図をさかのぼると、ヘラクレスなどが出てくる。ギリシャ神話に至るのである。渡部昇一氏はドイツの留学時代に、ギリシャでは神話になってしまったが、日本では神の系図が今の天皇家にそのままつながるのだ、とクラスの中で豪語して、周囲の学生らから尊敬を受けたとどこかで述べている。九〇年代後半の氏の言論である。
系図を神話、伝承にさかのぼることが出来るというのは、いかに日本が古代から一貫したものであるかが確認できることかもしれないが、近代、モダーン・ソサエティというものを作り上げた西洋から見てみると、いまさら何を夢のようなたわごとを言っているのだろうか、と言うことになる。
渡部氏はワールド・ヴァリューズの視点から見れば、「ロマンティック(romantic)=バカ」にすら数えられない、前近代性を脱皮できていない日本知識人、と言うことになる。あれだけ西洋の大学で教育を受けていながら、である。
名誉革命以後の王位継承は「ジェームズ一世の子孫」に決まった―神の系図など在りえるものか
いずれにしろ「リベ保守」の本当の継承理念の原点が、「国民の自由の確保」に基づいていることが分かったであろう。バークがプライスを批判したのは、プライスがこれを捻じ曲げて、「国民が我々の為政者を選ぶ権利、自由」としたことである。これは間違いである。
名誉革命でイギリスの王位についたメアリーによる王位継承の数年後に、「権利の宣言」で保障された理念が、再び現実に試される機会が到来する。先のメアリーの妹、アン女王から世継ぎが生まれなかったのである。アンはメアリーとウィリアム死後に国王となった。
この時からおそらく現在まで、イギリスの継承法は「ソフィア選帝公女とその子孫に、プロテスタントである限り、王冠を授与」(『省察』 四八ページ)することになった。これは一体何を言っているのか。
これは「イギリスのスチュワート家の創始、ジェームズ一世のプロテスタントの子孫にイギリスの王冠を継承させる」という意味である。ジェームズ一世は、ジェームズ二世の三代前の王である。もとはスコットランド王であり、メアリー・スチュワートの子である。
ジェームズ一世は子のチャールズ一世に王位を継承させるが、別にエリザベスという娘がいた。エリザベスはプファルツ選帝候フリードリヒの妃としてスウェーデンに嫁ぐ。
エリザベスの娘ゾフィー(英語でソフィア)は、初代ハノーヴァー選帝候エルンスト・アウグストの妃としてドイツに嫁ぎ、その子供がゲオルグ・ルートヴィヒという。
イギリスの王となっていたアン女王には子供が生まれなかったため、系図を綿密に吟味して、ジェームズ一世から連なる、ハノーヴァー王家のゲオルグに王冠を継承させることになった。これが名誉革命後の王位継承の経緯である。
男系、男性のみの継承は「継承」の本質ではない
ゲオルグはイギリス王ジョージ一世として即位し、このとき現在のウィンザー朝に連なるハノーヴァー朝が始まったのである。この後一八世紀の間、ハノーヴァー朝歴代王は実質ドイツ人なので、ドイツ語しか話せず、内閣による政治主導が発達した。彼らはドイツにばかりいたようである。
ウィンザー朝とは、イギリス王家の別荘のあるところの地名で、第二次世界大戦の時にハノーヴァー朝から改名された。
イギリスの近代王位継承法がさかのぼれるのは、一七世紀、ジェームズ一世からだというのはこのような事情からなのである。ここには聖書も、アーサー王伝説も、ゲルマン部族社会の先祖も存在しない。
スチュワート朝以前のイギリス王家は、日本でいう諸大名の有力者程度にしか過ぎず、イギリスは一六世紀以前、実質的に部族社会、トライバル・ソサエティ(tribal society)だったのだろう。
チューダー、スチュワートからさかのぼった王位継承が最も近代的なのである。異国であるドイツ、オランダにまで王冠を捜し求めることも厭わない、厳格な王冠継承(国民の自由、権利、安寧の保障と不可分に結びついている)こそが近代的なのである。(そもそもイギリスの本当の独立した歴史自体が一六世紀から始まる。)
日本の場合、本来は朝鮮半島に天皇家の源が求められてしまうのだろうが、万世一系、古事記という伝承にその系図を求めるのなら、異国に天皇を捜し求めるといったことは起こり得ない。
何を男性、男系にこだわっているのだろう。これではパトリアーキアル・トライバル・ソサエティ(patriarchial tribal society)、父系部族社会だと言わざるを得ない。
これは前近代社会(プレ・モダーン・ソサエティ)を意味する。副島氏の言うように、近代の訪れていない日本に、ポスト・モダン思想などあったものではない。
名誉革命以後の「継承」の本当の意味は、くどいようだが「財産の継承」である
イギリスの継承が一七世紀、ジェームズ一世からのプロテスタント家系に限ると言うのは分かった。ではイギリスの「継承」とは一体何なのか。神や伝承にさかのぼることのない「継承」とは、一体何を相続するのかを述べて行きたい。
近代に確立されたイギリスの継承思想とは、王冠の継承に伴なって「我々の一切の保有物を先祖からの相続と財産として引き出すこと」(『省察』六一ページ)である。その理念はイギリス法の最初である「マグナ・カルタ(Magna Carta)」から連綿と続いている、とバークは述べている。
イギリスの国民は、古代から受け継がれてきた「最も神聖な権利や特典を、相続財産と考えてきた」(『省察』六二ページ)である。この考えは、国王大権(徴税権、公債の発行、逮捕権など)を拡大したチャールズ二世に対して、議会から嘆願というかたちで提出された。これを「権利の請願」(ペティション・オブ・ライト、Petition of Right、一六二八年)という。
「権利の請願」はチャールズ一世第三年の法律といって、「陛下の臣民はこの自由を相続してきた」と、このときに公的に「継承」の考え方がはっきりと述べられたのである。
古来の先祖から相続されてきた、イギリス民衆の財産とは「自由」なのである。「権利」と言い換えてもいい。ロックによって「自然権」として財産継承の自由に、近代的解釈が施されたのである。
バークの言葉を借りると、「我々の古来の疑うべからざる法と自由の確保、つまり、我々の法と自由の唯一の保障にほかならぬ、統治の古来の憲法の維持のために達成された」ということなのである。
イギリスの近代継承法は、国民の自由と権利に結びついている。このことが大事なのである。自然権を保障するために、王家の正統に王冠を継承させるのである。それはチャールズ一世から続くプロテスタントの家系に受け継がせることによって、初めて保障される。
ここにプライスの言うような「我々自身のための統治形成の権利」の入り込む余地はない。プライスの思想は、ルソーのジェネラル・ウィルと人権思想である。正統の継承と民の自由、権利が結びついたイギリス法とは明らかに違う。
バークをいくら読んでも「自然法」という言葉が見当たらないと言ったが、その代わりに古来と言う言葉が頻出する。それが出てくるのが、このプライスの三つ目の主張への反駁である。
「権利の宣言」には、「ここに主張され宣言される権利と自由が、一切残らずこの王国の民衆の真に疑いの余地なき、古来の権利と自由である旨を、宣言され制定されるように」と書かれている。
この「古来」という言葉を指してホッブズ、ロックから続く近代的「自然法」と同一視してはならない。バークの「自然」(先に述べた「自然の衝動」)とは、人間が古来から持つ自然の感情のことである。
自然に先祖から継承されてきた社会制度、慣習、そして財産を「人定法によって積み上げられてきた家産」として自然に継承しよう。そのように「権利の請願」と「権利の章典」で規定されたのだ、ということなのである。
だから私、鴨川は、師匠である副島氏を補足、批判しなければならなくなるのだ。副島氏が『覇権アメ』で述べた「永遠の相の下の」、アンダー・ザ・エターナル・アスペクトという意味での自然法は、古代のアリストテレスから続く思想であり、本質的にバークのものではあり得ない。
この「永遠の相の下の」自然法思想はアリストテレスに限らす、イエス・キリスト(Jesus Christ)や釈迦(Buddha)の思想に連なる。近代を超えたところにこのエターナル・アスペクト(eternal aspect)という言葉があるのだ。
人間自体を大切にする思想のことである。
副島氏自身も二年ほど前から、そのように自己の思想の修正を図っている。そのことの本当の意味を私鴨川はここに明確に述べて、この稿を終えようと思う。
次はジェレミー・ベンサム、J・Sミル(J.S. Mill)について述べ、政治哲学が政治科学、ポリティカル・サイエンス(political science)に移行した経緯を述べていきます。
(つづく)